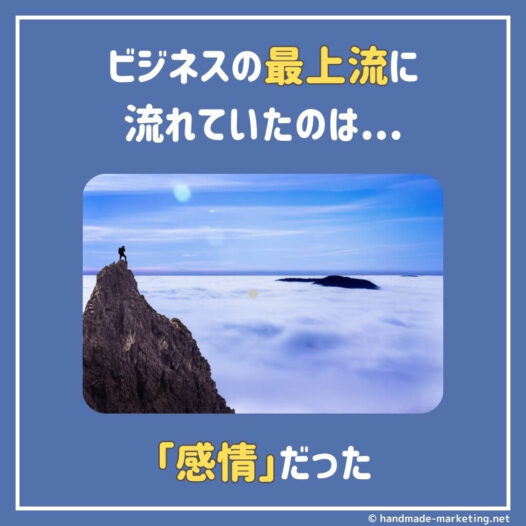
今回は、趣を変えた記事にしようと思います。
テーマは、「ビジネスの最上流」について。ビジネスを突き詰めていくと、1番上には何があるのか?
おそらく作家さんの多くは、ビジネスが得意な人ほど、「数字」や「分析」の世界に身を投じるイメージがあると思います。SNSで人気作家っぽい人は、アクセス解析がどうとか、リーチ数がうんたらとか、数字を意識した発言も多い。
もちろん、ボクもそういう経験はしましたよ。50シートくらいあるエクセルで、何十億円の収支を1円単位から計算したりしてました。
しかし、さらにビジネスの山を登り続け、分厚い雲を抜けて、辿り着いた頂上から見渡したら、そこにあったのは「感情」が支配する世界だったのです。
この話は、いつものように「なんとかの法則」とか「なんとかのフレームワーク」みたいな説明では伝わりません。ボクの個人的なエピソードからお伝えすることにしましょう。
本編は29〜31歳の話ですが、前段から始めて足掛け10年弱の話です。
- 中小企業営業時代(24〜26歳)
- 大企業営業時代(26〜29歳)
- 社内ベンチャー立ち上げ時代(29〜31歳)
ステージが上がるごとに、ビジネスの階段を登ることになります。そして3段階目の「ベンチャー立ち上げ」のときに、天上界の世界を見ました。
この天上界は、多くの人にとって未知の世界です。これまでの人生で出会ったことのないような超エリート達、「人生何周目?」という頭キレキレのビジネスパーソンが、何を見ていたのか?
ボクのコンテンツをよくチェックして下さっている読者さんは、ボクが人一倍「ブランド」や「ストーリー」に執心しているのはお気づきでしょう。ボクがこのビジネス哲学に至った原点の話です。
いつもは、「ですます調」だけど、今回に限っては、「である調」でやってみようかと
エッセイっぽい感じで!
【注意!】お読みいただく前に
- めちゃくちゃ長くなってしまったので、初見の人には辛いと思います。ボクのコンテンツを見て、ボクに多少なりとも興味を持ってくれた人に向けた記事だと思ってください。
- その時々でお世話になった方々の個人名を出していますが、全て仮名となっています。
0章:誰の目にも向いてなかった営業マンになって

話の中心は、ボクが社内ベンチャー立ち上げに身を投じていた頃。
…なんだけど、その手前から話を始めよう。
ボクは伝統的に金融機関への就職に強い大学で、経済学部だった。特に深く考えることなく、先輩に倣って、ボクも金融機関メインで就活をしていた。
しかし、ボクが就活する年は、運悪くリーマンショックに見舞われて、状況は一変。金融機関に限らず、あらゆる業界の採用が狭き門になってしまった。ゼミの1つ上の先輩までは、半数がメガバンや大手証券会社へ内定をもぎ取っていたが、同期15人ほどでメガバン内定1人という有様。
もはや第何志望かわからないくらいだったが、大手通信キャリアに内定をいただいた。正直行きたかった企業ではなかったが、この就職難で大企業に入れただけでも御の字だった。
配属されたのは、法人営業部隊。当時の新人はほとんどが営業配属だったので、既定路線に入ったわけだ。
ボクの性格は、はっきり言って営業に向いていなかったと思う。
ボクの性格を物語るエピソードを紹介しよう。
ボクは5歳くらいのとき、人形焼が食べられなかった。なぜかと言うと、生き物の形をしているものは、かわいそうで食べることができなかったんだ。「かわいい顔」がついているお菓子は、基本食べることができなった。
童謡の『かあさんの歌』の「母さんが夜なべをして、てぶくーろ編んでくれたぁ…♪」って聞くと必ず泣いちゃうの。お母さんが辛い思いをしているのは嫌だって。
こんなのもある。小学校3年生くらいだったかな?
年上のいとこ姉妹と、浅草に遊びに行ったんだ。200円お小遣いをもらって。で、その場で焼いているお煎餅が美味しそうな匂いがしていて、すっごく食べたかった。50円のお煎餅。
でも、決断できなかった。お店の人に声をかける勇気がなかったのかもしれない。しかも、その日は200円のお小遣いとは別に、道端で50円を拾っていたのに!
臆病で、繊細で、人付き合いが苦手で。1歳の頃からボクを知っている幼馴染のお母さんも、「なおちゃんが営業なんて、大丈夫かしらねぇ」と漏らしていたと、後から聞いた。
ボク自身も、自分に営業職が務まるとは思っていなかった。
しかし、スマホが世に出たばかりで、まだ日本人の9割がガラケーだった時代は、「文系の新卒は営業」と相場が決まっていた。他に選択肢がなかったので、開き直って受け入れるしかない。
配属当初は、今では絶滅しかけているであろうテレアポ&飛び込みの新規営業から始まった。もう苦痛でしかなかった。もちろん成果も出なかった。
ただ、やっと掴んだ初受注の女性担当者が、ボクの教育係だった5つ上の先輩と良い仲になり、結婚するという後日談がある。図らずも、お世話になった二人のキューピッド役になれたことは、心から光栄に思う。
…話を戻そう。
テレアポ&飛び込みは、いわゆる新人への洗礼イベントで、言ってみれば研修みたいなもの。営業配属の3ヶ月後には、担当企業を抱えるルート営業になった。
1章:中小企業営業時代

24〜26歳までの約3年間、東京・神奈川の中小企業のルート営業となった。規模感としては、社員10〜500名程度の企業がお客さん。30〜150名くらいがボリュームゾーン。
課長の山梨さんは、当時37か38歳。とても厳しく、そして仕事ができる上司だった。
課内でメンター(教育係)としてついてくれた富山さんは、ちょうど一回り年上の36歳。こちらも仕事はできるが、山梨課長と比べると優しい人柄だった。
やっぱり営業はしんどかった!
山梨課長からは、「1日3件お客さん訪問しろ!それがお前の最初の仕事だ!」と命じられた。
これ、感覚わからないかもしれないけど、1日3件法人にアポ取って訪問って、かなり難しい。正直、「え?冗談でしょう?」と思った。でも、全く冗談じゃなかった。
お客さんだって、用もなく会ってはくれない。向こうだって仕事が忙しいから。それに、アポを取るって言っても、即日なんてのはない。大抵は1〜2週後に取る。今日の明日で3件なんて行けるわけがない。
白状すると、ボクは1日3件の訪問はできなかった。でも社内にいると「何で会社にいんだよ!」と怒られるので、とりあえず外に出るしかなった。
何とか1日1件はアポを取り、それ以外は外で仕事してた。たまに、山梨課長と富山さんとボクのチャットグループに、「今どこいんの?」と確認が入る。これが怖くてビクビクしてた。多分、ホントは3件も訪問できていなかったって、バレてたと思う。
山梨課長は、あらゆる所作に厳しい。
部長に呼ばれて、大きな声で「はい!」と返事したら、イスを蹴っ飛ばされた。「呼ばれたら、走って部長んとこまで行くんだよ!」と怒られた。確かにボクが悪いな。
数字の詰めも厳しい。
「おそらく来週で決まると思います」なんて言った日には、150kmのカウンターボールが返ってくる。「来週のいつ?何日?確度は何%?客はどこでスタックしてるんだ?次のアポは?」と。
とにかく口酸っぱく言われたのは、「ロジカルに話せ!数字で示せ!」だ。
そして、山梨課長のもう一つの口癖が、「言い訳すんな!」である。なんと、この上司は言い訳も許してくれないんだ。弁解はさせてもらえない。
「できない理由なんて聞きたくもない。そんな言い訳考える暇あったら、どうやったら課題をクリアできるか考えろ!考てから話せ」だ。
まだ若くて甘ちゃんのボクは、「サイコパスかよ…」と思ったけど、山梨課長は人に厳しいと同時に、自分にも厳しい。もちろん言い訳なんかしない。ビシッと筋は通っていた。だから、文句は言えなかった。
それでも、1年目の新入社員にはちと厳しかったように思うけど。
こんなとき、ボクの心の支えになってくれたのが、メンターの富山さん。終電が近づいてくると、「ヤバい時間だ!」って言いながら一緒に駅のホームまで走った。帰り道がほぼ同じだったので、色々と相談に乗ってもらった。
富山さんは、1回りも上の36歳で、お子さんも二人いて、土日は家族サービスしている。自分も激務な上に、ボクの面倒まで見ている。本当に頭が上がらなかった。
折れない心
実際に営業をやってみて、「やっぱり向いてないなぁ…」と思っていたんだけど、意外なことに、営業向きな才能も持ち合わせていたみたい。
「メンタルの強さ」と「地道にコツコツ続けられる生真面目さ」という才能だ。
これだけ聞くと、素晴らしい才能に聞こえるかもしれない。しかしその代わりに、愚鈍で要領が悪く、人付き合いが苦手で、ガラスのハートを持っている。そんな良いものじゃない。
ここで不思議に思ったかもしれない。
ボクは「ガラスのハート」の持ち主だ。ちょっと小言を言われるとか以前に、相手の顔色がほんの少し曇るだけで傷つく繊細な性格をしている。
にも関わらず、なぜかメンタルが強かった。ガラスのハートが叩かれる度に、ジンジンと響いてひどく苦しい思いをしたが、なぜかハートが砕け散ることがなかった。血だらけになりながら歩くのだが、なかなか倒れない。
重くて面倒なお客さんを担当させられても、連日連夜の深夜残業をさせても、ノルマ未達で鬼詰めされても。ボクの心は折れることがなかった。
ボクが勤めていたこの会社、今では完全なるホワイト企業へと変貌したが、当時の営業部隊はブラック労働上等。同期や先輩の中には、辞めていく人、会社に来れなくなる人、ギブアップして配置換えを願い出る人が後を絶たなかった。
ボクはそれを横目に見て、「あの人はギブって言えたんだ…羨ましいな…」と思っていた。
何度も言うが、繊細な人間なので人一倍傷ついてはいる。しかしメンタルが強すぎて、根を上げるところまでいかない。イメージ的には、茨道を歩く巨人といったところだろうか。伝わる人は、漫画『BLEACH』のアスキン・ナックルヴァールを想像してもらっても良いかもしれない。
この才能というか性格は、幼少期の家庭環境によるところが大きいと思う。
ボクの両親は共にサラリーマンで、生後2ヶ月から保育園に通っていた。〜90年代前半の世相では、子どもを保育園に通わせる家庭は、自営業(主に個人商店)かシングルマザーのどっちかだった。
お勤めしている女性は、結婚すると寿退社して専業主婦になるのが普通。だったけど、母はやめなかった。何でかはよくわからない。経理だったので、好きな仕事をやってたわけではないと思う。
保育園の友達は、親が近所で仕事しているので、17時には迎えに来る。しかし、母は終業後に電車で帰ってくる。お迎えは19時近くで、いつも1番最後まで残っていた。担任の先生も帰っちゃって、園長のおばあちゃん先生と2人で。
そんなわけで、両親と過ごした時間が短く、親に甘えたり、ねだったりした記憶が全くない。「欲しいものある?」と聞かれて、ようやく、それも控えめに答えるような子どもだった。
そのせいか、今でも他人に上手にお願いできない。とにかく要領が悪い。自分の努力だけで何とかしようとする。それでどうしようもなければ、運命を受け入れるメンタリティになっている。
このメンタリティで小さい頃から生きてきたせいか、耐え忍ぶことに耐性がついてしまった。コツコツ継続できるのも、人に頼らないで生きるために、そうせざるを得なかったんだと思う。
こういうタフな職場では、メンタルが強いヤツは放っておかれない。次々に、重くて大変なお客さんを当てがわれるようになる。
ここで、もう1つの才能、「地道にコツコツ続けられる生真面目さ」が効いてくる。
ボクにとっての「お客さんのための当たり前の対応」は、他の営業から見ると「優等生な特別対応」だったようだ。他の営業がテキトーすぎるだけだと思うが、兎にも角にも、ボクはマメにお客さんをケアし続けた。
事実、ボクが担当から外れるとき、ほとんどのお客さんが「え〜!いなくなっちゃうんですか!?残念ですぅ」と言ってくれた。会社としては良くないことだが、ボクが担当を外れて、後任の対応に不満を抱き、解約になってしまったお客さんもちらほら。
重いお客さんは、手間もかかるし、精神もすり減らす。けど、数字はついてくる。そして、さらに重い担当企業をあてがわれていく。この繰り返し。
こうして、誰の目にも営業に向いていなかったボクは、ゆっくりと営業部隊内でプレゼンスを発揮するようになった。
ずっとここでいいかも…
今にして思えば、中小企業の営業はイージーだった。相手はその辺のおっちゃん、おばちゃん、にいちゃん、ねえちゃん。他所も大した営業は通ってない。
小まめにケアできて、社会人としてごく普通の水準のコミュニケーションが取れれば、ちゃんと成果につながった。仕事の遅さは、労働時間でカバーできる。
もちろん、ボクに営業のいろはを叩き込んでくれた、山梨課長と富山さんのおかげだ。これは後から気づいたことだが、本部で優秀な人を挙げたら、この2人がツートップだったと思う。厳しい基準を持った2人が納得する仕事をすれば、お客さんも納得するし、他の営業よりも質の高い仕事ができた。
2年目には重要な戦力になってたし、3年目にはエース級になっていたと思う。途中から山梨課長は部長に昇進し、富山さんが課長になった。本部内で1番できる課長と1番できるメンバーだから、当然の昇進だったと思う。富山さんに関しては、他所のへっぽこ課長よりもずーっと優秀だったんだから、遅すぎるくらいだ。
ボクはそのまま富山課にスライドしたわけだが、課長も仲良しで、メンバーの先輩も仲良ししかおらず、サイコーの居心地だった。仕事のやり方も大々わかっていたし、普通にやっていれば、上位の成績も取れる。
「あー、ずっとここでいいかも…」
そう思い始めた矢先。この平穏は長くは続かなかった。
突然、大企業向け営業本部に異動することになったんだ(※これまでは、中小企業のルート営業)。
現部署の本部長からの「頑張ってる若いヤツに、もっとチャレンジさせたい」という計らい。単なる配置転換ではなく、本部長の愛ある采配だった。ボクに目をかけてくれていたんだ。本当にありがたい。
ただ、当の本人は異動を求めていなかったのだけど…。
2章:大企業営業時代

大手通信キャリアは、「通信インフラ」という商材の性格上、日本全国ありとあらゆる企業をお客さんとして抱えている。社員1人の零細企業から、社員何万人の誰もが知る大企業まで。
異動先の営業本部は、そういう誰もが知るスーパー大企業を担当する。
魑魅魍魎の住まう魔窟へ
ボクが配属されたのは、とある金融グループを担当する営業部隊。あまりにも大きすぎるので、10人ほどの営業がそのグループ企業を手分けして担当する。その1人にノミネートされたんだ。
そしてここは、全社でもトップクラスにハードなことで知られる魔窟だった。営業が10人いると言ったが、半年に2,3人が脱落していくので、コロコロと担当が変わっていく。若い営業マンだけでなく、30代40代の営業マンでも根を上げる。
結論から言うと、ボクはこの魔窟に、26〜29歳の3年間在籍した。最後は引き抜かれての異動だったので、自分の意思ではない。というわけで、ここでも耐え忍んだことになる(何でギブできないのかねぇ…)。
この魔窟は、「耐えて昇進するか。さもなくば潰れて脱落するか」の2択しか存在しない。ここの管理職は、魑魅魍魎クラスの化け物しかいなかった。
直属の上司は目黒課長。年は36歳だったと思う。山梨課長も凄まじく仕事ができる人だったが、目黒課長はさらに凄かった。おそらく、全社でもトップクラスの営業マンだったと思う。実際、目黒課長は、この後スピード出世することになる。
これが大企業の営業だ!
お客さんの質も随分変わる。
中小企業で相手にするのは、その辺のおっちゃんおばちゃんだったが、大企業で相手にするのは、高学歴のビジネスマンだ。そして、金融系というのは、特にお作法に厳しい。官公庁の次くらいに厳しい。また、他所の営業マンもレベルが高いので、求められるハードルも2段3段上がる。
もうね、とにかくめんどくせーんだ。
イメージ的には、今まではコップを取り出して、ジュースを注いで渡せばよかった。ジュースが美味しければ、それで何も問題なかった。
それが、まずコップは冷蔵庫で冷やしておいて、氷はコップの大きさにすっぽり入るように丸く削っておく。これを仕損じた時用に、もう1セット用意しておく。あらかじめここまで注ぐという位置を決めておき、ビンのラベルを上にしてジュースを注ぐ。手渡しだとミスってこぼす危険性があるので、お客さんの利き手の方に置いて渡す。
ジュースが美味しかろうと、こういう所作ができなければ通用しない。
ひょっとすると、「形ばかり気にしてアホらし」と思われたかもしれないね。ボクも最初はそう思ってたよ。でもそうじゃないんだ。このお作法には、全て意味がある。
イメージしやすい例を出そう。業務用iPadを配るとする。
30人の会社に配るなら
iPhone使ってればiPadの使い方もわかるだろうし、若い人なら、操作で困ることもないだろう。気を使うのは、高齢の役員くらい。
担当者1人でケアすれば済むレベル。困ったら、担当者からボクに1本電話を貰えば良い。その日は電話を受け取れるように、予定を空けておこう。
何なら、ボクが現地でサポートすることもできる。そこまでやったら、大感謝される。これが中小企業の営業だ。
これが大企業となると、何千、何万という社員に影響する。
ほんの些細な、トラブルとも言えないレベルのつまづきでも、担当者や営業1人では対処しきれない。事前に潰せるリスクは全て潰す。
大企業に配るなら
iPadの設定は、あらかじめ業者に依頼して、お客さんの社員が受け取った時点で、すぐに使い始められる状態にしておく。業務に不必要なアプリは、あらかじめ削除しておく。
操作方法の研修を用意して、講師はこちらで用意する。その様子を録画しておき、後から見られるようにアーカイブを残しておく。
本当に規模が大きい場合は、コールセンターまで用意する。そして、そのコールセンターの想定問答を作って、その場で答えられる内容は答えてもらい、答えきれない質問は、エスカレーション(その場で完結せず、本部に問い合わせてもらう)させる。もちろん、エスカレーション先は事前に決めておき、専用のメールアドレスも用意しておく。
店舗などで使う場合は、電波状況が悪いと業務に差し支える。あらかじめ電波状況を確認し、悪い店舗には電波改善の工事も手配する。また、新店舗ができる際は、電波チェックして、悪い場合は即座に工事に入れるように、運用フローも建て付けておく。
もちろん、iPadを紛失してしまった場合の対処も決めておき、発覚した瞬間に、ロックをかけたり、データ消去したりする。これも、利用者がどこに連絡して、誰がどう対処するのか、事前に運用フローを整備しておく。
…と、これでもパッと思い出せる内容を書いただけで、他にもうんとたくさんある。
導入した後の流れを想定し、その先でつまづく可能性のある石を一つ一つを取り除いておく。走り出しす前に、つまづく石のないキレイな道路にしておかなきゃいけない。
そこまでしないと、お客さんは納得しない。というより、そうしないで走り出すと、お客さん担当者が地獄を見ることになり、社内評価も下がる。もちろん、売った営業も信頼を失う。
だからこそ、このお作法は、必要不可欠なプロセス。何手も先を読み、重箱の隅どころかフタの裏まで気を配らせる。お客さんがパッと思いつくような質問は、事前に回答を用意しておくのが当然。そうやって、お客さんの最善にコミットする。
こういう気配りができる営業だけが、信頼を勝ち得る。これが大企業の営業だ。
怒られてるうちが花
ハッキリ言って、中小企業相手では上手く回っていたボクの営業は、全く通用しなかった。お客さん担当者を怒らせて、後から目黒課長に「なんだ!あのなってない営業は!」とクレームがあったらしい。
このクレームをつけてきたお客さんは、浦和さんという。50代の老兵で、司馬遼太郎のようなキレイな白髪で、気難しいそうな顔立ち。
この浦和さんには、何度も何度も何度も怒られた。今どき机をバンバン叩いて怒る人がいるとは思わなかったので、本当にビックリした。
飲み好きで、よく終電後まで付き合わされた。キャバクラを自腹で奢らされたこともある。酒癖がメチャクチャ悪く、なんと顔面を殴られたこともある。気弱なボクも、流石にキレそうになったが、グッと堪えた。
とんでもオヤジなんだけど、愛があった。酒の場は行き過ぎとしても、普段叱ってくれるのは、ボクに客の立場から営業の仕方を教えてくれていたんだ。
契約書を作るときは、ボクが素案を作った後、「よし、一緒に読み合わせしよう」と、1行ずつ読んで、「この文言はどういう意味だっけ?」と確認し合った。普通はこんなことしない。でも、こういう経験のおかげで、契約書作りにも強くなった。
目黒課長も同じ。たくさんの試練を与えられて、たくさん失敗して、たくさん怒られた。3年間の在籍期間中、怒られなかった日なんて数えるくらいしかなかったと思う。
目黒課長からは、「怒られるのは期待されてる証拠。見放されたら誰も怒らなくなる。怒られてるうちが花だぞ」とよく言われた。今にして思えば、紛れもない真実だった。
もしあなたにお子さんがいるなら、分かると思う。人を叱るのって、すごく嫌だし、面倒だし、出来ることならやりたくない。愛のない相手なら、叱るまでもなく距離を取るだけだろう。
もしボクに見切りをつけたら、怒るまでもなく、別の人間に変える。これは営業部もそうだし、お客さんもそう。お客さんから「担当変えろ」と言われたら、基本的には従わざるを得ない。
でもそうはならなかった。出来の悪いボクを期待して、辛抱強く育ててくれたんだ。
耐え抜いた先の果実
とは言っても、毎期誰かしらが会社に来れなくなる過酷な労働環境には変わりない。もう、メチャクチャしんどい。
会社で終電近くまで働き、一度帰って夕飯と風呂を済ませたら、深夜2時辺りまでまた仕事する。でも終わらない。熟睡すると間に合わないので、電気つけたまま仮眠し、5時に目覚ましをセットする。眠い目を擦りながら続きの仕事…。
「明日やろうは馬鹿やろう」という言葉をご存知だろうか?「今日できる仕事は、今日のうちにやる。明日に伸ばすヤツは成功せんぞ」という意味。
でもここでは、そんな言葉は幻想。追われるタスクが尽きる瞬間は、永遠に訪れない。明日できる仕事は明日に回さなければ、一睡もできずに朝を迎えることになる。
こういう日々だった。徹夜もしばしばあった。とても1人の人間には背負いきれない、身の毛もよだつようなクレームも何度かあった。
前の中小企業ルート営業のときは、最後は「しばらくここでいいや」と思っていた話した。しかし、ここはそんなことはなく、常に逃げ出したいと思っていた。
ついにダメかと思ったが、ここでもボクは耐えられてしまった。ギブしていれば、また違う人生になっていたと思うんだけど、なかなかそうならない性分らしい。
途切れることのない1000本ノックを打たれ続け、最後まで立ち続けた。毎日試練を与えられて、毎日失敗して、毎日階段を1段ずつ登っていった。振り返ったら、3年前にこの魔窟に来たときよりも、遥か高い場所まで登っていた。
頭の回転が遅く要領が悪かったボクだったが、これだけ過酷な環境に身を投じれば、いやでも地力はつく。他の営業マンとは真逆の性格だったボクは、こうして1人前の営業になった。
ここのお客さんは、格別にキツい代わりに、格別に大きな数字がついてくる。魔窟に来て3年目、昨年対比の売上で、ボクは全社1位の成績を収めた。2,000人いた営業マンの中で、第1位になったんだ。
一応言っておくと、ボクが凄かったのではなく、担当企業に恵まれていたのと、目黒さんをはじめとした上司が有能だったからだ。しかし、このとびきり重たい企業を任せられる営業マンは、100人に1人くらいしかいなかったと思う。そういう意味では、ボクもいくらかは凄かったのかもしれない。
このときのボクは、まだ会社の歯車に過ぎなかったけど、とびきり大きく、とびきり丈夫な歯車になっていた。齢29。夏のボーナスは300万円。年収は1,000万円を少し超えた。
3章:新規事業の世界へ

ボクが魔窟に来て3年目、前年の大型案件を経て、次の案件に着手していた頃、会社では極秘裏にある計画が進められていた。
会社の未来を担う次世代事業を立ち上げるため、精鋭だけを集めた「X部隊」を作ろうという計画だ。イメージ的には、「アベンジャーズ」みたいな感じ。ごく一部の幹部しか知らない、極秘計画だった。
さらば!営業!
まず、全国で2,000人いる営業マンのうち、上位10%の精鋭がノミネートされた。次に、彼ら彼女らは役員の面接を受けることとなる。ただし、当の本人はそんな面接とは知らされず、単に「現場の意見を聞かせてほしい」という体での面談だった。
同じ本部で、30前後の若くて成績優秀なメンバーが4人1組になり、役員1人から質問を受ける。書記の人もいたように記憶している。色々聞かれたが、「ぶっちゃけ営業もうキツい…」という本音だけは隠しつつも、割と素直な気持ちを答えた。何を聞かれて何を言ったのかは、よく覚えていない。
そして魔窟に来てちょうど3年が過ぎようというときに、目黒課長から「ちょっといい?」と空いている会議室に呼ばれた。このとき目黒さんは部長に昇進していたので、目黒部長になっていた。
そこで、目黒部長の口から、「X部隊」への異動の内示を受けた。あの役員面談が、X部隊への最終面接だったということも、ここで知らされた。そもそもX部隊という組織が秘密裏に計画されていたことも、ここで初めて知らされた。
目黒部長からは、3年間目をかけて育ててきた部下を、唐突に手放すことになった複雑な心境を打ち明けられた。きっと、次に任せたかった案件もあったろう。悔しい気持ちが滲み出ていた。
当のボクはというと、心身共に疲れ切っていた。何度も繰り返すが、ガラスのハートの持ち主には、あまりにも辛い職場。そろそろ真剣に転職を考え始めていた頃合いだった。
X部隊が何するところかよくわからなかったが、兎にも角にも魔窟から離れられる嬉しさで、心の中ではファンファーレが鳴り響く。しかし、目の前で悔しい心境を吐露する目黒部長に、そんな素振りは見せられない。気持ちが表に出ないよう、神妙な面持ちを崩さぬよう努めた。
こうしてボクは、新卒以来6年半に渡って従事してきた法人営業を、唐突に卒業することになったんだ。
人生最良の師
幹部肝入りの「X部隊」に配属され、新しい日々がスタートする。
が、何をするのかよくわからない。わかっていたのは、
- 「新規事業で売上を作ること」
- 「当社の株価を上げること」
が目標だったということ。
つまり、細かい話は決まってない。 「各々、我が道を切り開けい!」みたいな状態笑
日本でも有数の大企業の幹部陣が、よくこんな詰まってない状態で見切り発車したなと、唖然としてしまった。ただ、VUCAの時代に、まっさらな頭で新規事業に取り組む意義は大きい。
※VUCA(ブーカ)とは?
- Volatility(変動性)
- Uncertainty(不確実性)
- Complexity(複雑性)
- Ambiguity(曖昧性・不明確さ)
の4つのキーワードから頭文字を取った用語。予測が難しい現代の世相を表している。
この「X部隊」を率いる本部長は、こんなフワフワした状態でも、会社には「◯年後までに、〇〇〇億円の売上を作ります!」とコミットしているはずだ。その重圧たるや、下々のメンバーには想像を絶する。「X部隊」の本部長と、その背中を押した幹部陣の思い切りの良さは、評価に値するのかもしれない。
…というわけで、フタを開ければ、「何でも良いから売上作るアイデアを考えて来い!」という放置プレイだったわけだが、意外なことに、ボクにはこれが性に合っていた。
幼馴染のお母さんが漏らしたように、やっぱりボクの脳みそは営業向きじゃなかったらしい。じっくりと腰を据えて、新しい何かを考える「クリエータータイプ」だったようだ。
同僚のみんなは、営業としてはこの上なく優秀だ。ボクより遥かに営業センスに溢れている。しかし、誰の指示を受けるでもなく、0ベースで「何をすべきか?」という問いを突きつけられたときに、彼らは思考停止していたように見えた。
同僚たちは、これまで担当していた馴染みの企業に、AIやらIoTやらRPAやら、当時キャッチーだった先端技術の提案をしようとしていた。部課長もそういう方針だった。しかし、それはこれまでの営業の延長線上に過ぎない。
「新規事業ってそういうことなの?何か違くね?」と思いながらも、これというアイデアも確信もない。しょうがないので、渋々上司の方針に従っていた。
そんなとき、1つのターニングポイントが訪れる。
田所雅之さんという、ベンチャーキャピタルの方が、「新規事業の作り方」というテーマで公演に来てくださった。田所さん自身も、ベンチャー企業立ち上げを経験してきている。
そこでボクは、これまで悶々としていた答えを聞いた。
『事業は技術から始まるんじゃない。顧客の課題から始まるんだ』と。
「うわあぁあああ!!!」と、心の中で唸り声を上げてしまった。ひょっとすると、口からちょっと漏れてたかもしれない。それくらい衝撃だった。
それまでは、AIやらIoTやら、あるいは通信キャリアが持っている「技術」を使って、お客さんの会社にどんな提案ができるか?という目線で考えていた。
そうじゃない。お客さんが欲しいのは「技術」じゃない。頭の痛い「課題」を解決したいんだ。その手段として、技術や製品を求めている。
いの一番に考えるべきは、技術でもトレンドでもなく、お客さんの課題なんだと。今では当たり前すぎで、知らなかったことすら恥ずかしいんだけど、当時のボクにはコペルニクス的な大転換だった。
この話は、ハンドメイド作家にも通ずるところがある。技法がどうとか、そもそも手作りかどうかさえ、お客さんにとってはどうでもいいこと。お客さんの唯一の関心ごとは、その作品が、自分の課題を解決したり、欲求を満たしてくれるかどうか。それが全てだ。
同僚たちは、「そういう考え方もあるんだねー」くらいの感覚だったようだが、ボクは公演が終わっても興奮が治らなかった。座ったまま考え込んだり、立ち上がってブツブツ言いながらフラフラ歩いたり。ボクの脳内は、事業アイデアの種が目まぐるしく交錯していた。
田所さんは『起業の科学』という本を出版されたばかり。ということで、帰りの電車で即ポチった。1ページ読むごとに、目から鱗がボロボロと落ちた。
実は、この『起業の科学』は、ボクが社会人になって最初に読んだビジネス書だ。
恥ずかしながら、29歳になるまで、ビジネス書など読んだことはなかった。というより、それまで仕事が好きじゃなかったので、本を読んでまで勉強しようという気が起こらなかった。
しかし、今回は違った。0からビジネスを立ち上げることに、心の底からワクワクしていた。寝ても覚めても、帰りの電車も、お風呂の時間も、とにかく事業のことが頭から離れない。夢の中でさえ事業企画をしていた笑
古代ローマ時代のセネカという偉人は、『過去の英知を手にするために時間を使う人は、自分が生まれる前に過ぎ去った時間を、自分の年月に付け加えることができる』と述べている。
あぁ、なんと素晴らしい言葉か。偉大な先人が、試行錯誤の末に掴んだ成功の法則を下敷きに、自分の経験を付け足せる。なんて尊いことだろう。
今までは、山梨さん、富山さん、目黒さんという、優秀な上司がいた。ボクにとっての最大の幸運は、新入社員から「上司ガチャ」でS級レアを引き続けたこと。わからないことは、上司が答えを持っていた。浦和さんのように、愛を持って大人の営業を教えてくれるお客さんもいた。
しかし、今は頼れる人はそばにいない(一応補足しておくと、X部隊の上司も優秀なんだけど、それは営業としてであって、新規事業はド素人だからって話ね)。
でも大丈夫。偉大な先人が、本の中からボクに語りかけてくれる。
ピクサー作品の『レミーのおいしいレストラン』をご存知だろうか?
主人公のネズミ・レミーは、ある日、5つ星レストランのシェフであるグストーの料理本を拾う。既にグストーは亡くなっているのだが、本を開けば、偉大なシェフ・グストーが語りかけてくれる。どうすれば美味しい料理を作れるかを。
ボクはレミーと全く同じ気持ちになった。本を開けば、ドラッカーが、コトラーが、デール・カーネギーが、ビジネスで大切なことを教えてくれる。
このときから、ボクは本を師として仰ぐようになった。今でも読書を最良の学びと位置付けているが、その原点はまさにこの瞬間。きっとこの先も一生涯、本は最良の師であり続けるだろう。
…とういうわけで、ビジネス書を読み漁り、そこで得た知識を新規事業の企画に活かすというサイクルがスタートする。
「X部隊」には、優秀な元営業マンがひしめき合っていたのだが、意外なことに、ビジネス書を読んで勉強しようという人はほとんどいなかった。わざわざ本を読んで勉強しようという社会人は珍しいらしい。だから、10万部でもベストセラーになる。社会人は何千万人もいるはずなのに…。
同僚はみな、センスと経験だけを頼りに、事業案を検討していた。そんな中でボク1人は、日々読書によって培われた知識をフル活用して、事業を検討していた。
同僚がソリューション営業もどきをしている中、ボクだけが、「顧客は誰で、その顧客の課題は何なのか?」をずーっと研究していた。
そして、かつて担当していたヘルスケア系の企業で話を聞く機会を得て、「ここだ」と確信する。課題の巣窟で、取り組むべき社会的意義があり、我が社のような大企業のニーズを満たす市場規模のポテンシャルがあった。
ボクは急いで企画資料を描き上げた。パワーポイントで50枚くらい。営業時代に散々鍛えられているので、もともとパワポは得意。それに輪をかけて、プレゼン資料作りの本で構成を学んだ。
ざっくりと、次のような展開だったと記憶している
- まず日本のヘルスケアに渦巻く大きな社会課題を挙げる
- その主たる原因はここにあると説く
- その原因を取り除き、社会課題を解決できるソリューショ案を提示す
- そのソリューションはこの技術によって実現可能であると説く
- その業界には、これだけの市場ポテンシャルがあると数字を見せる
- まずはここから攻めるという、最初のとっかかりを定める
- 将来的にはここまで拡大させるという青写真を提示する
今にして思えば、あまりに粗く、事業企画の体はなしていなかった。壮大で、夢ばかりで、具体性に欠けていた。詰めは甘々だった。
まずは直属の課長に披露した。X部隊での新しい上司になった高松課長だ。歳は38歳くらい。高松課長は、これまでの上司とはちょっと雰囲気が違う。
かつての山梨課長や目黒課長は、このまま営業を続けていたら、ボクも30代後半にはこうなるのかなという想像ができた。いや、山梨さんや目黒さんほど剛の性格じゃないので、優しい富山さんみたいな営業マンになってたんじゃないかな。
でも高松課長は、ボクの延長線上にはいないタイプだった。天性の人たらしで、人脈作りの天才。人付き合いが苦手なボクには、絶対にマネできない。こう言うと、人柄だけに聞こえてしまうが、もちろん精鋭部隊に召集されるくらいなので、一角の営業ではない。お作法の厳しい官公庁のお客さんを相手に、目を見張る成果を積み上げてきた一流の営業マンだ。
ボクと高松課長は、互いに足りないものを補い合うコンビだったと思う。
高松課長は、不勉強だが、地頭がメチャクチャ良い。一方で、ボクは地頭は悪いが、勉強熱心だった。高松課長は直感で閃くタイプだが、ボクはじっくり考えて結論を出すタイプだった。高松課長は資料作りが苦手だったが、ボクは大得意だった。
ボクは、高松課長の直感と人脈を頼りにした。高松課長は、ボクの思考力と資料作成能力を頼りにした。上司・部下の立場は理解しつつも、最後まで対等な関係であり続けた。
地頭が良い高松課長は、ボクの資料を見て、「あ、これが俺たちの仕事なんだ」と確信したようだ。
そして、「お前は、もう上から落ちてきた仕事はやんなくて良い。このヘルスケアの企画に集中しろ」と。
「あ、そうそう、これ酒井本部長にも見せるぞ」とも。
酒井本部長は、「X部隊」のボス。このときで40代前半で、30代で営業本部長まで出世した正真正銘のバケモノ。超絶に頭がキレる。
プレゼンの結果、1から100まで粗いところを挙げられて、ボッコボコにされた。
グサリとやられたのが、「虫の目が足りない」と。
ビジネスの世界には、「鳥の目」と「虫の目」という言葉がある。鳥の目は、鳥のように俯瞰して大局をつかむ目。虫の目は、現場の個々人のアクションまでつぶさに落とし込む目。
「お前らが虫の目でチマチマしたこと言ってたら、俺は、『鳥の目で見ろ』と言う。鳥の目だけの大風呂敷だったら、俺は、『虫の目で見ろ』と言う。で、お前は虫の目が足りない」と。当然のご指摘である。
しかし、このときのボクは若かったし、ある種の無双モードに入っていた。そのせいか、いま思い返すと畏れ多いことだが、本部長にいちいち喰ってかかった。
- 酒井本部長「ここが足りねーって言ってんだよ」
- なお「じゃあ、あの本部長肝入りのあの案件はどうなんですか?満たしてるなら教えてくださいよ」
ただ、酒井本部長は満足げな顔をしていた。高松課長もにんまりしていた。こういう展開を待っていたのかもしれない。
「とにかくやり直してこい!」となったわけだが、これは「GO(進めろ)」という意味でもあった。
ボクたちは何のために存在するのか?
ヘルスケアプロジェクトの最初期メンバーは、ボクと高松課長と、2個上の松戸先輩の計3人。最終的には100人以上になるわけだが、初めはたまたま同じ課内にいた3人で始まった。
松戸先輩は、同じ高松課のメンバー。たまたま営業時代にヘルスケア系企業を担当していたという理由で、チームを組むことになった。今までの登場人物に比べると、頭のキレるタイプではないが、ガッツがあり、誠実で、信頼できるマイルドヤンキーだ。
初めは、たった3人しかいないメンバー間でも考えがチグハグで、全く前に進まなかった。
そこで、メンバーで腹を割って話すことにした。夜も20時を過ぎる頃になると、会議室は予約なしで使い放題。深夜静まり返った社内。夜食をつまみながら、延々と語り合った。
「ボクたちは、一体何のために存在しているんだろう?」と。
こういうビジネスをする上での、最上位の目的、存在理由のことを、
- 「パーパス」と呼ぶこともあるし、
- 「ミッション」と呼ぶこともあるし、
- 「理念」と呼ぶこともあるし、
- 「大義」と呼ぶこともある。
みな意味は同じ。ちなみに、ボクは「ミッション」を使うことが多い。
ふわっとしていて、つかみどころがないと思われるかもしれない。朝礼で復唱させられるイメージかもしれない。世間では、「そんなの気持ちも問題でしょ?意味あるの?」と思われている節もある。
断じて否。ミッションは、最上位の意思決定だ。
自分達の存在理由を考えない人は、真に0→1で価値を創造しようとしたことがない人だ。誰かが作り上げた価値にぶら下がっているか、あるいは相乗りしているだけだ。
こう考えてみてほしい。企業が、その企業でいられなくなるのはどんなときだろう?
例えば、ユニクロを展開している「ファーストリテイリング」が、ファーストリテイリングでいられなくなるのは、どんなときだろう?
- 社長が変わったら?
- 創業者の柳井さん引退したら?
- 社員が全員入れ替わったら?
- あの名物フリースが売れなくなって撤退したら?
- 全てがオワコンになって、社員1人になってしまったら?
どれも違う。
「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」というミッションを見失ったときだ。ミッションこそが、企業の核(コア)なんだ。全く新しいビジネスで、全く新しい価値を見出すためには、絶対にミッションから考えなければならない。
ミッションは、憲法の第一条みたいなもの。何があっても背いてはいけない。言動も行動も、ミッションから伸びる一本の筋を通さなければならない。仮に、背いた先に儲かる道があったとしても、断固として跳ね除けなければならない。
ミッションは、絶対にブレることのない指針であり、羅針盤であり、北極星だ。どんなに迷っても、ミッションを思い出せば、どの道を歩むべきか、あるいはどの道は自分には相応しくないか、いつでも教えてくれる。
ホワイトボードに書いては消して、書いては消して。先輩後輩も、上司部下も関係なく、タメ口で、あーでもないこーでもないと。ちなみにボクが1番年下ね。
疲れたらコーラで糖分補給して、ダレたらクソみたいなギャグでゲラゲラ笑って。ちょっとガラの悪いメンバーだったので、下品な話もした気がする。ボクは下ネタあんま好きじゃないんだけどね。
一晩じゃ結論は出ないので、毎晩のようにメンバーで飲みに行って語り合った。高松課長と松戸先輩はレモンサワー。ボクは下戸なのでウーロン茶。ボクは当時独身だったけど、高松課長と松戸先輩は妻子持ちだった。家庭は大丈夫だったんだろうか?
言葉にしたらたった1行で済むミッションを、大の大人が何日もかけて語り合う。なんだかおかしいな話だよね。ドラマみたいでしょ?
そして、ようやく自分達らしいミッションが見つかった。「てにをは」や語呂まで気を配って、「よし、このために全てを捧げよう」と思える言葉だ。これから毎日のように繰り返し口にすることになる言葉。そして、多くの人の心を動かすことになる言葉だ。
で、肝心のミッションの内容なんだけど…、忘れてしまった笑
あれから随分経ってるし、会社も辞めてるしね。
イメージ的には、「テクノロジーの力で医療費を削減し、日本を持続可能な国する」みたいな感じ。当時はまだ「SDGs」というスローガンが世に出る前だけど、近しいニュアンスがあった。
そうやって、自分たちの存在意義を見つけて、羅針盤が指し示す方向が定まったとき、歯車は動き出した。
ある日のお昼時に、酒井本部長から「ちょっとこっちこい」と呼び出しが入る。ボクと高松課長と松戸先輩の3人は、本部長席に駆け寄る。
- 酒井本部長「〇〇って企業知ってるか?」
- なお&高松課長&松戸先輩「知らないっす」
- 酒井本部長「いいか、説明するぞ。こうこう、こういうことやってる会社だ」
- なお&高松課長&松戸先輩「はい」
- 本部長「この会社と組んだ事業案を副社長に話したいから、お前らが考えろ」
- 高松課長「いつまでですか?」
- 酒井本部長「今日の3時(15時)」
- なお「あと3時間しかないですけど…」
- 酒井本部長「ポンチ絵1枚でいいから。この企業のことは気にぜず、ヘルスケアでデカい構想を描け。できたらすぐに見せろ」
- なお「わっ…かりました」
ちなみに「ポンチ絵」とは、提案内容を1枚で表現した概念図のようなもの。曼荼羅(マンダラ)は、仏教の世界観を1枚で表現したポンチ絵とも言える。
ポンチ絵は経験が必要で、上手に描けないビジネスマンが多い。コンサルや霞ヶ関の官僚が得意としているもので、ロジカルシンキングが不可欠。しかし、ボクの営業時代のお客さんは、個別・複雑・大型案件が多かったので、0からパワポを作ることが多く、ポンチ絵を自分で描く機会が多かった。実は、ポンチ絵は得意だった。本当に、営業時代に培った経験は宝物だ。
- 高松課長「あと3時間で描けそう?」
- なお「とりあえず1時間ください。素案描きます」
そう。このプロジェクトのブレーンはボクなので、この役回りは、ボクの仕事なんだ。高松課長もそう思っていたろうし、ボクもそう自覚していた。
3時間は、粗めのポンチ絵を「描くだけ」なら十分な時間だが、問題は「何を描くか?」という案の方。3時間で、副社長を唸らせる案を出さなきゃいけない。
ボクは、これまで調べ上げてきたヘルスケアの領域を束ねて、1つのデータベースで繋がる未来図を示した。ヘルスケアといってもさまざまな領域があるわけだが、それらが有機的につながり、この日本に巣食う巨大な社会課題に風穴を開ける構想だ。
あまりにも壮大で、何年かかるのかわからないし、そもそも実現できるのかも怪しい。理屈の上では実現できるが、技術や制度などの障壁が著しい。大風呂敷を広げすぎた感は反省しているが、間違いなくこれから先の日本に必要な青写真だったと今も思う。
兎にも角にも、苦し紛れではあったが、描き上げた。というか、1日猶予があっても、これ以上のものを描くことはできなかったと思う。
高松課長は一目見てOKを出した。修正はなし。
続いて酒井本部長にも見せた。OK。修正はなし。
酒井本部長「よし、時間になったら副社長に見せに行くぞ」
「え?ボクも行くの?」と思ったが、口には出さなかった。
副社長と言っても、うちは超大企業。そんじょそこらの社長よりもずっと格上の人。下々が会話することも滅多にない、顔を覚えてもらうことも難しい雲の上の人だ。
で、ビクビクしながら副社長が待つ部屋に入った。
幸いにも、酒井本部長が結構しゃべってくれた気がする。何を話したかはあまり覚えていないが、馬鹿みたいにウケたことだけは覚えている。副社長は、大風呂敷が大好きだったようだ。これ以降、このポンチ絵は副社長の大のお気に入りとなり、ことあるごとに「これだよ!これをウチがやるんだよ!」と声を荒くして言っていた。
ハンドメイドは「世界観が命」というけど、ビジネスとはそもそもそういうもの。副社長は、ボク達が描き上げた世界観に惚れ込んでくれた。以降、このポンチ絵は、ボク達の錦の御旗となって、あらゆるプレゼン資料の冒頭に差し込まれることになった。
そして、雲の上の副社長から、名前までは覚えられなかったが、「ヘルスケアプロジェクトの小僧」という感じで、顔は覚えてもらえるようになった。もっとも、丸坊主&丸メガネの風貌が目立っていたおかげでもあるが。
この辺りから、ボクがポンチ絵を描くのが上手いと認知されるようになり、また自分でもそう自覚するようになった。勝手ながら、「一級ポンチ絵師」を自称するようになった。もちろん、内輪だけの話だけどね笑
こうして、無茶振りを乗り越えたヘルスケアプロジェクトは、次のステージに進む。副社長のお墨付きももらって、正式に社内ベンチャーの立ち上げを目指すことになった。人数も3人から増え、7人の専任チームになった。
社内ベンチャーとは、社内から創業資金を出資してもらい、新規事業会社を立ち上げるということ。出資するのが内部というだけで、やっていることは起業と同じ。
今は、副社長から「ベンチャー立ち上げを検討しろ!」という「検討」の命令が下されただけ。あくまで検討段階であり、これで決まりじゃない。
事業を立ち上げるには、市場調査して、経済合理性のあるビジネスモデルを書き上げ、プロダクトの開発体制に目星をつけ、必要なビジネスパートナーを募り、社内外のあらゆるステークホルダーを口説き落とす必要がある。その上で、鬼門となる財務部門を納得させなきゃいけない。
全ての下準備を済ませ、資金が提供されたら即座に事業に取り掛かれる体制にした上で、経営会議という天上人の会議にかけられる。そこまでクリアして、ようやく社内ベンチャーが立ち上がる。
これから何十人と口説き落とさなきゃいけない中で、酒井本部長と副社長の2人だけが後ろ盾になってくれただけ。心強い2人だが、まだまだ先は果てしなく長い(→がっつりハショるのでご安心を)。
そして、ここから天上界に本格突入することになる。天上界最初の1人が、副社長だったということだ。
いざ、天上界へ!
ボクの最初のキャリアは、中小企業営業だった。このときは、天上界の人と接する機会は皆無。一番上が本部長。大企業の本部長は部下100〜300人いるので、凄い人ではある。ただ下っ端から見ると、上司(課長)の上司(部長)の上司(統括部長)の上司(本部長)なので、直接バチバチやり合うことはない。
続く大企業営業では、少し天上界の人々が垣間見えるようになった。大きな営業案件だと、先方の役員が同席することもある。ただ、基本的には現場同士のやり取りが多い。
加えて、商談のときも、相手が偉い人が出てくるときは、こちらも同格か1つ下レベルの人間を連れて行くのが通例。大企業の役員が出てくるなら、こちらも本部長を連れていく。そうなると、全体の流れを作るのはトップ同士。現場のボクは、説明役に徹することが多い。場合によっては、資料だけ作って出る幕がないときもある。
しかし、ここからは違う。
まず、これは既存事業の話じゃない。企業の組織は、既存事業を回すために最適化されている。わかりきっている業務なので、適宜現場に権限委譲されて、いちいち上の人間が指図することなく、現場で仕事が回るようになっている。
一方で新規事業は、当たり前だが、既存業務の範疇外だ。この話を、業務の一環として聞いてくれる現場の人はいない。そうなると、早々にキーマンクラスが登場する。社内では本部長クラスだし、社外では役員クラスが出てくる。
この人たちと、正真正銘ボクが対峙することになる。
なぜなら、このベンチャーを立ち上げるのは、ボクら数人のチームで、そのチームの中心的な役割を果たしているのがボクだから。ボクが話を切り出して、ボクがプレゼンして、ボクが鋭い突っ込みを浴びて、ボクが受け答えする。正確に言うと、ボクと高松課長と松戸先輩の3人が、こういう役回りだった。
ここで対峙するエリート達は凄いよ。テレビに出てくる人で、これまでの人生で見たことないような凄い経歴の人っているでしょ?ああいう人がゴロゴロ出てくる。
- 東大卒
- 帰国子女
- 起業経験者
- 外資コンサル出身
などなど。半分以上の人が英語ペラペラ。3カ国語話せる人もゴロゴロいた。
「え?東大卒の人ってこんなにいたん?」と思った。
東大医学部卒、医師免許あり、外資コンサル勤務を経て、スタートアップの代表みたいな人もいる。これまで約30年の人生で、1度も見たことのない超絶エリート。
パートナー候補に中国の企業もあって、何度も出張した。今は中国企業と組むなんてとんでもない世界情勢になっているけど、当時はまだ「進んでいる中国のITに習おう!」みたいな時代で、中国投資が活況だった頃だ。
中国の平均所得は日本より遥かに低いが、ボクらが対面している中国人エリートは、ボクよりも高給取りだ。先にも言ったが、ボクは20代で年収1,000万円に到達していたが、それより多い。ボクの2個上、当時で32歳で年収億越えの中国人もいた。
中国人エリートは、英語もペラペラだ。多分、留学でもしてたんだろう。「え?この10人の中で、英語しゃべれないのボクだけ?」というシーンも度々あった。
唐突に言語の壁が出てきて、どうやって乗り越えたのか気になったかもしれないね。猛勉強してしゃべれるようになったわけじゃないよ。社内で海外案件に強いチームが協力してくれていた。彼らには、大いに助けてもらった。
ちょっと余談。
本場中国のレストランは、八角などの香辛料が多用されていて、街中が独特の匂いに包まれている。ボクは割と中国食をエンジョイしていて、日本展開もしている「海底火鍋」がお気に入りだった。
ただ、中国の味付けが全くダメなメンバーもいた。そのため、ケンタッキーやバーガーキングによくお世話になった。あと、イタリアンは日本で食べられるものと変わらないので、これもおすすめ。
日本料理屋もあるが、出汁が効いていない見せかけで、「出汁って偉大だな」とみんなでしみじみ呟いていた。
真のビジネスエリート達は、今まで見てきた人種とはホントに物が違う。
さっき「大企業のサラリーマンでも意外と勉強してない」って言ったけど、この人達は間違いなく今でもビジネスの勉強をしている。ボクが昨日今日ビジネス書で知った話は、当然インストールされてて、その上で実践を積んで成果をもぎ取っている。正真正銘のビジネス界のサイヤ人だ。
頭のキレも半端ない。少しでもロジックが途切れると、すぐさま「あ、そこちょっと詳しく教えて」と差し込んでくる。100枚のスライドを用意(必ずしも全部説明するわけじゃないが)して、こちらが「実はここが煮詰まってないんだよな…」と思っているところを、針を刺すように突いてくる。この人たちには何も隠せない。
当たり前に、数字には超絶シビア。
一番シビアだったのは、うちの会社の財務。我が社は日本でもトップクラスに投資額の大きな会社だったので、財務は当然キレッキレ。何度突き返されて、何度苦渋を舐めたか。もちろん、協力してくれる仲間なので、とっても感謝しているけど笑
本当に何度も突っ込むから、向こうもだんだん協力的になってくれたりして。財務の本部長もボクのことを覚えてくれるようになって、エレベーターで会うと「順調?待ってるからね!」と声をかけてくれるようになった。
ちなみに、この財務と話す資料は、「NPV(割引現在価値)」という投資対効果を計算するエクセルシートが主。NPVでは、例えば「5年後に50億円の利益が出る案件は、現在なら何億の価値があるか?」を計算する。
5年後の50億円は、現在の価値に直すともっと低い金額になる。それはなぜか?
例えば、現在50億円を国債などの無リスク資産に投資したら、年1-5%程度の利息がつく。仮に2%としよう。すると、1年後は51億円になる。5年後は55.2億になる。端数の0.2億は、複利によって増えた分だ。
逆に、5年後の50億円は現在に直すと、45.3億円になる。これは、「5年後の50億円のNPV=45.3億円です」という言い方になる。
ただし民間企業の場合は、この計算に自社の資金調達コストを加味する。例えば、銀行から借り入れたり、社債を発行したり、株式を発行したり。そういったコストを鑑みて、さらに割り引くことになる。
…と、つまらない説明はこれくらいに。こういう計算を、50枚くらいのエクセルシートを使って、1円単位でしてたって話ね。
既存事業の追加投資なら、このNPVで精緻な計算ができる。例えば、通信ケーブルを追加で1本敷設する話だと、需要も単価も概ねわかっているので、確度の高い計算ができる。こういう案件は、財務も納得しやすい。
しかし、これは新規事業だ。5年後の収支計画?そんなの絵に描いた餅にしかならない。どこまで精緻に書いても、やってみなきゃわからないし、99%その通りにはならない。
ここで、「スモールビジネス」と「ベンチャー/スタートアップ」の違いに触れておこう。
「スモールビジネス」は、みんながよく知っている既存のビジネスを小さく展開することで、それなりの利益を得ようとするやり方。例えば「地元で飲食店を開く」とか、「大工が独立して工務店を立ち上げる」とかいう話だ。ハンドメイドもスモールビジネスだし、個人のネットビジネスもスモールビジネスだ。
一方で「ベンチャー/スタートアップ」は、まだ世にない新しいビジネスを打ちたて、短期間に大きく成長させるやり方。大袈裟に言えば、未来のGoogleやFacebookを立ち上げるようなもの。日本で言えば、会計ソフトのfreeeやメルカリがスタートアップ型だ。
スモールビジネスは、個人の収入としては十分魅力的だが、大企業の収益源には足りない。ボクらが所属する「X部隊」は、我が社の未来の柱になる事業を作ることだ。どうしたって「ベンチャー/スタートアップ」型のビジネスになる。
これは覚えておくと良い。世の中は、「リスク」と「リターン」が必ず正比例するようにできている。自然の摂理なので、例外はない。大きなリターンを狙うには、必ず大きなリスクを背負い込む必要がある。
もし正確に収支を予測できるとしたら、それは既に一定規模の市場があり、誰かの前例があるということになる。特大の実りを狙うためには、先が読めない事業に身を投じざるを得ない。
これはどうしようもないこと。できることと言えば、投資額を抑えて小さな市場から入り、なるべく長く戦えるようにするくらいの話だ。
この事情は、ボクらベンチャー立ち上げ側も、財務側も、同然ながら理解している。だから、市場調査の結果や、インタビュー結果などを用いて、その蓋然性(=確からしさ)をストーリーで補足するのだが、やっぱり絵空事からは抜け出せない。
ちなみに、財務が飛び切り数字に厳しいのは当たり前として、口説かなきゃいけない他のビジネスエリート達も、数字に厳しいのは変わらない。細かいエクセルシートまでは見せないだけで、同じように収益のストーリーを話して納得させなきゃいけない。
さて困った…。
今までの営業では、「弊社のサービスを使えば、〇〇〇万円削減できます!」「人件費を〇〇億円削減できます!」みたいなのが多かった。1,000万円の効果があるなら、500万円の契約をするという判断は、営業にとってもお客さんにとってもわかりやすかった。数字の確からしさこそが、最終的な拠り所だった。
しかし、今回はその数字をいくら詰めたところで、豆腐のようにフニャフニャとしたロジックにしかならない。今までのように、数字こそが唯一絶対の信じられる指標でなくなってしまった。
新入社員時代の山梨課長も、「ロジックだ!数字だ!」と言った。次の大企業営業の時の目黒課長も、「ロジックだ!数字だ!」と言った。その通りだ。この天上界のエリートは、すべからくロジカルシンキングの権化。ロジックなしでは太刀打ち不可能。ロジックで語れなきゃ、ここまでこれなかったし、相手にもされなかった。それは紛れもない事実。
しかし、ロジックだけでは通せないところまで、ボクは来てしまった…。
ビジネスの最上流に流れていたのは「感情」だった
では、どうやって彼らを動かしたのか。
「感情」だ。
知っての通り、ヘルスケア業界の闇は大きい。国のもっとも大きな支出は医療費だ。人口が増えていく前提で作られた制度は、現役世代が高齢者を支える構図になっている。かつての人口ピラミッドは、高齢者が少なく、若者が多かったので、4-5人で1人のご老人を支えればよかった。それが、1人の若者が、1人の高齢者を背負わなきゃいけない時代に差し掛かろうとしている。
その重荷を背負うのは誰か?
あなたの子供達、あるいは孫達だ。
ビジネスエリート達は、30代後半から50代が多い。やはり役職が上になる程、年齢層が上がっていくので、中高生の子供がいるケースも多い。子供が成人していて、孫がいる人もいたかもしれない。
彼らはビジネスで成功してきたので、多少割り食っても逃げ切れる。しかし、あなた方の子供はどうだ?孫達はどうだ?
沈むのがわかっている泥舟を、次の世代に託すのか?
斜陽になった国を、苦笑いしながら我が子や孫に引き継ぐのか?
成功したあなたが最後にやるべき仕事は、次世代の人たちがもっと幸せに暮らせる国にして、気持ちよくバトンタッチすることじゃないか?
…と、ストレートに言ったわけではないけど、こう感じざるを得ないプレゼンになっていたと思う。狙ってやったわけじゃないけど、ボク自身が正義と熱意に駆られていたので、自然と感情を揺さぶる話し方になっていたのかもしれない。
「そうだ…!これは絶対に、誰かがやらなきゃいけない仕事だ…!」
多くの人から、こういう言葉をもらった。社交辞令には聞こえなかったし、演技にも見えなかった。本心からの言葉だったように思う。
プロジェクトの仲間に、GMOグループから転職してきたメンバーがいる。その人から聞いたのだが、GMOグループ内には、「あなたに解決できない問題は、そもそもあなたには起こらない」という言葉があるらしい。
その通りだ。天災や国際政治の話は、ボクの身には降りかからない。それはボクにコントロールできない問題だからだ。受け入れるか逃げるかしか選択肢がない。
この話が出たということは、ボクもあなた(社内外ビジネスエリート達)も、この難しい問題を解決できるかもしれない立場にいるからだ。難しいかもしれないが、可能性は0ではない。その「誰か」は、ボクであり、あなたではないのか?
このプロジェクトのビジョンは壮大で、産官学の連携も必要になる。大企業の体力が必要だし、それにはITの力も不可欠だ。我々がやるのに、十分な理由ではないか?
大企業の役員クラスと聞くと、数字に支配された機械のような人間を想像するかもしれない。事実は違う。彼らも人間だ。熱いハートを持っている。承認欲求だけで出世のモチベーションは続かない。むしろ人一倍強いハートを持っていると思う。
中国出張のとき、たまたま他所の本部長と2人でタクシーに乗り込むことになった。普通ならド緊張するシチュエーション。初対面なら尚更だ。しかし、頭がヒーローモードになっているボクは、いつもとは違う積極性を見せた。
「この移動時間で、ちょっとだけボクの話を聞いていただけないでしょうか?」
資料なしで15分ほどプレゼンした。問題ない。もう何百回も話した内容だ。緊張はしたが、澱みはなかった。
「わかった!日本に帰ったら、もう1度詳しく聞こう。アポは秘書経由で入れてくれ!」
こんな泥臭いことして、仲間を増やしていったんだ。
重要なパートナー候補の企業にプレゼンした日は、今もよく覚えている。相手は、社員何万人を抱えるヘルスケア系企業の重役だ。白の面積の方が多い白髪混じりのヘアスタイルで、歳の頃は初老だったが、長身でバイタリティあふれる人物。前のめりでプレゼント聞いてくれて、手応えを感じた。
翌日、「君のプレゼンに心が踊って、昨夜は眠れなかった」というメールが届いた。営業時代に、こんな言葉をもらったことは1度もない。超一流の営業マンでも、こんな言葉をもらったことがある人はいないと思う。
この頃は、メンバー皆心身ともに疲れ切っていたので、メールを開封した瞬間は、心の奥底まで沁みた。涙が溢れそうになったが、オフィス内だったので必死に堪えた。
「大丈夫。応援してくれてる仲間がいる。俺たちはまだまだやれるぞ!」って。すっごく背中を押された気がした。
もしボクらが、「〇〇億円儲かるから一緒にやりましょう!」と誘っていたら、誰1人として乗らなかったろう。みな、ミッションに共感したからこそ、一緒に荒波を越えたいと思ったんだ。
…この先は蛇足になるから駆け足で。
なんやかんやで仲間を増やし続け、経営会議に付議するところまで来た。ここまで来たということは、難関の財務も含め、あらゆる関係者を納得させて、出資金さえ振り込まれれば「GO」できる状態まで持っていったということ。
ここに至るまで、何千枚スライドを描いたかな?何百回プレゼンしたかな?熱く熱く、想いをたぎらせて、雲の上にいる人達の「心」を動かして、ようやくここまで辿り着いた。
この「経営会議」が、まさに「天上界の会議」だ。当時の本社は25階建で、経営会議専用の大会議室も25階にある。物凄い広さで、体育館よりは狭いが、25mプールよりは広かったと思う。
経営会議に参加できる人を「ボードメンバー」と呼ぶが、彼らがまさに天上人。ここまで来ると、ボクは発言を許されない。高松課長(このときは部長格に昇格していたが)がスピーカーになって、ボクと松戸先輩は後方で待機だった。
自分で話はしないものの、プレゼン資料はボクが大部分を作ったもの。それがそのまま使われる。正直怖かった。
粛々と経営会議は進み、ボクらのプロジェクトが議題に上がる番。経営会議自体は和やかなものだが、ボクらの緊張感は最高潮に達していた。手汗をほとんどかかない体質だが、このときばかりは手に汗を握っていたと思う。スピーカーの高松課長は相当なプレッシャーだったろう。
プレゼンが終わり、ボードメンバーの1人が意見を述べた。
込み入った話になるが、出資比率の話だった。実はこの社内ベンチャーは、「JV(ジョイントベンチャー)」で、他の会社との共同出資によって立ち上げることになっていた。
この出資比率に対し、「うちがもっと比率高い方が良いんじゃない?」というご意見。別のボードメンバーも「俺もそう思う」と同調した。これが厄介で、その意見に応えようとすると、調整し直さなきゃいけない。計画が大幅ディレイすることになる。
正直に言ってしまうと、承認が降りる前提で関係者への調整を進めていた。あまり適切ではないが、現場ではよくある話。ここで計画が遅れると、関係者に多大な迷惑がかかるどころか、ひょっとすると話自体が頓挫することにもなりかねない。
この出資比率は、事情があって、現場のボクたちは関与しておらず、やんごとない人達の間で取り交わされている。そのため、高松課長は何も言えない。笑顔は絶やさないが、引きつっているのが見てとれた。ボクも全く同じ気持ちで、背筋が凍りついた。
一瞬の沈黙が走る。たった数秒の沈黙だったが、永遠のように感じた。
「やばい…、やばい…、このままだと終わる….」
そのとき、左手の方から手が上がる。ボクたちの味方になってくれているボードメンバーの1人だった。
詳しくは話せないが、これが素晴らしいカウンターだった。
指摘には理解を示しつつも、この出資比率がかなり複雑な経緯で決まっており、今から調整すると面倒を背負い込むことになる。もし必要なら、一旦スタートさせてから増資して、当社の出資比率を増やすこともできる。これが現実的ではないか?
こんな感じ。
意見をくれたボードメンバーは納得してくれた。余談をすると、このご指摘は本当にその通りで、後々うちの出資比率を高めておけば良かったというシーンに遭遇することになる。脱線するので割愛するが、やはり天上人の経験値はスゴい。
緊張が走った場面はあったが、ボクたちのプロジェクトは無事に経営会議を通過した。社内ベンチャーの立ち上げが確定したんだ。
もちろん、ここからがスタート。この後もまぁ大変だった…。
が、このスタートラインに立つまでも本当に、本当に大変だった。ここまで辿り着けたことは、過去の自分を褒めても良い1つの成果だったと思う。
営業時代の仕事は、もちろん頑張ったが、ボクじゃない別の人でも取って代われたと思う。それこそ、優秀な上司ならもっと上手に回せただろう。上司の仕事を手伝っているシーンも多かった。
しかし、このヘルスケアベンチャーの立ち上げは、まさしく自分の仕事だった。たくさんの人に支えられた結果であることは間違いないが、ボクなしで立ち上がったかと言えば、そうならなかったと思う。
ただ、あまりにも大変なので、もう1回やってくれと言われたら丁重にお断りしたい笑
【結び】あなたに伝えたいメッセージ

一旦、エピソードトークはここまでとしよう。
臆病で、慎重で、人見知りで、いつも斜に構えてたボクが、あれほど情熱を燃やして、あれほど大胆かつ泥臭く駆け回って、あれほど多くの人を巻き込んだ。
奇跡としか思えない。いま思い返すと、あれは夢か幻だったんじゃないかとさえ思う。
そのベンチャーはちゃんと立ち上がって、今もある。ボクは思うところあって、この2年後に会社を去ったけど、笑顔で握手した円満退社だ。
この記事を書くにあたり、久しぶりに去った会社のホームページを眺めた。プロダクトは随分拡張されていて、見た目もずっとキレイになっていた。これをボクがやった仕事だと言うのは無理があるだろう。後に続いた人たちの頑張りによるものだ。
あれからもう随分時間が経っている。ボクを知っているのは、一部の古参メンバーくらいだろう。ボクは完全に過去の人。ボクなんか全く必要とすることなく、この会社は立派に回っている。
しかし、会社のミッションやビジョンに目をやると、そこには変わらず、あの頃の想いが残っている。羅針盤の向きは、今でも、初期メンバー3人が居酒屋で語り合ったときのまま。この会社を駆動させているコアには、今でも29歳のボクがいる。
「あぁ、やっぱり自分が作った会社なんだな」としみじみ思った。
考えることも含めて制作だ
ここからが、ボクのメッセージ。
自分が何者で、誰のために、どんな未来を届けるのか。
なぜ自分はそうしたいのか。
なぜ自分じゃなきゃいけないのか。
自らが果たすべき役割を決めて、決してブレない軸を持つ。全ての言動と行動に、一本筋を通す。
それが、どれだけ大きなパワーを生むか。どれだけ人の心を熱くさせるか。ボクは身をもって経験した。
ビジネスと聞くと、いかにも「数字」とか「分析」みたいな頭固そうなことを追求するように思うかもしれない。けどそれは、ビジネスの一部の面に過ぎない。
ビジネスライクを追求すると、行き着く最後のてっぺんは「感情」の世界になる。ビジネスの最上流を支配しているのは、「エモさ」なんだ。
このサイト名は「ロジカルハンドメイドマーケティング」で、「ロジカル=論理的」と謳っているのに、「感情」が1番大事って、矛盾してない?と思われたかもしれないね。
実は、全く矛盾していない。
ボクのビジネスロジックの中には、「感情」というピースが含まれている。感情をいかに、ロジック立ててビジネスに落とし込んでいくか。これが、ボクの1番の関心事であると同時に、ボクにしか言語化できない領域だと思っている。
この感覚は、経験しないと確信を持って言葉にできない。そして、こういう経験をした人は、とーーっても少ない。企業でも上層部の人か、新規事業やベンチャーの立ち上げフェーズに主戦力として携わった人にしかわからないと思う。
そういう人が、ハンドメイドのような個人ビジネスの世界にやってくることは、基本ない。ハンドメイド界隈で、ボク以外にいるのかな?
個人ビジネスの世界にもインフルエンサーはいるけど、あの人達は、あくまでスモールビジネスで成功した人。例えば、ブログとかYouTubeとか動画編集とかデザイナーとか、そういう既に需要があることがわかっている場所で、手堅くやってきた人だ。
動画編集は、動画編集のスキルと、ごく普通のビジネスコミュニケーションができれば仕事は成立する。そういう人達の発信は、小手先ばかりの話、ビジネスで言えば下流の話。言い方を変えれば、それで通用する世界ということ。
では、ハンドメイドブランドはどうだろう?
卒ないスキルさえあれば、作品は売れるだろうか?
そうじゃないことは、あなたもよく知っているはず。
用を足すだけなら、安い既製品で構わない。100均でも構わない。それでもあえて、10倍や100倍の値段を払うのは、「用」ではなく、「心」を満たす商品だから。
ハンドメイド作品は、お客さんの「心」を満たさなきゃならない。お客さんの「感情」に訴えかけて、「これがほしい!」と思ってもらわなきゃいけない。
巷でありがたがられてるテクニック論は、所詮は枝葉に過ぎない。テクニックも必要だけど、あくまで小手先の話だ。テクニックで人の心は動かせない。
ブランドコンセプトを固めて、一途にその通りに行動した軌跡がブランドのストーリーになる。これが、これだけが、人の「心」を動かせる。
しかも、テクニックの賞味期限は、短いと数年か、下手したら数ヶ月しか持たない。一方で、ストーリーに心を打たれるのはホモサピエンスの習性だから、1000年経っても変わらない。
クリエーターのあなたには、この事実をよくよく知っておいてほしい。ボク自身はモノづくりはしていないけど、分類すれば一応クリエーターだから、これを言う資格はあると思う。
ただ作っているだけじゃダメだ。小手先のテクニックに逃げてもダメだ。
一度立ち止まって、自分自身を深く見つめ直して、自分が向かうべき羅針盤の向きを定めなきゃいけない。
脳みそにたくさん汗をかこう。
クリエーターにとって、考えることも含めて制作だよ。ここが、他人に言われた通りに作る下請けとの1番の違いだ。指先は、脳で考えた構想を、実現するためにある。創造は、指先じゃなく脳から生まれるんだ。
あなたの生き様は何だ?
大企業営業時代のお客さん、浦和さんを覚えているかな?
白髪の50代で、営業のボクにキャバクラを奢らせたり、飲みの席で顔面パンチを食らわせてきたとんでもオヤジだ。同時に、愛を持って育ててくれた人でもある。
この浦和さん、酒が入るとすぐに説教モードになる。3ヶ月に1回くらいのペースで飲み会がセットされるんだけど、毎回同じ言葉を浴びせられる。
「お前の生き様を言ってみろ」
これを毎回言われるの笑
浦和さんは金融系のシステム畑を歩いてきた人で、古来からのシステムエンジニアリングを愛している。これが俺の生き様なんだと、前のめりで口走ってくる。典型的な、昔話したい系オジサンね。
そして、「お前はどうなんだ?お前の生き様を言ってみろ」と。
めちゃくちゃウザいでしょ笑
20代の頃のボクに、生き様なんてなかった。そもそも入りたくて入った会社じゃないし、好きでやってた営業でもなかった。だからテキトーに流してた。
でも今ここで、ボクはかつての浦和さんと同じことを、あなたに問おう。
「あなたの生き様は何だ?」と。
さっきも言ったことを、説教くさくもう一度言う。
自分が何者で、誰のために、どんな未来を届けるのか。
なぜ自分はそうしたいのか。
なぜ自分じゃなきゃいけないのか。
これが、「生き様」だ。
ベンチャー立ち上げの頃は、ボクはヘルスケアの未来を変えることに死力を尽くした。これが、当時のボクの生き様だった。
でも、今は違う。
「生き様が変わるのってどうなの?」と思ったかもしれないね。まぁいいじゃない。人生長いんだから、途中で考え方が変わることもあるって笑
ここでスティーブ・ジョブズの伝説的なスピーチ『コネクティング・ザ・ドッツ(点と点をつなぐ)』を紹介しよう。感動的なスピーチで2-3年に1度、思い出したように聞く。もし聞いたことがなければ、YouTubeで検索してみると良い。
趣旨をカンタンに伝えるならこう。
人生は、運命のイタズラで様々な方向に転がっていく。どんな未来が訪れるかは、誰にも予測できない。対峙している瞬間には悪夢としか思えないような経験もする。
しかし、その時々の経験(点)が、なぜだか1つの線つながって、将来の自分の道になる。つながると信じて、いま目の前にあることに精一杯取り組もう。
ポジティブに解釈した「人間万事塞翁が馬」ってとこだね。
ジョブズ自身、実の親に養子に出されたり、せっかく入った大学を中退したり、自分で作った会社を追い出されたりしている。
しかし、それらの経験が全て有機的につながり、ジョブズはAppleを時価総額世界一の企業にまで押し上げた。
ジョブズの後だと些細な話になるが、ボクも、点と点がつながった経験をしている。
就活生の時は、金融機関を志望していたが、折しもリーマンショックと重なり、その道は絶たれてしまった。結果として、第何志望かわからない通信キャリアに入社することになった。
配属されたのは法人営業。誰が見ても営業には全く向かない性格だったが、この時代の文系学生は、営業配属が相場と決まっていた。
どうせ上手くはいかないだろうと思ったけど、…そうでもなかったみたい。
ボクは、幼少期に両親と共に過ごす時間があまり長くなかったせいか、甘えるのが苦手な子に育った。これはそのまま要領の悪さにつながるのだが、その反面、忍耐強く、コツコツできる特性があった。
この強みは、臆病さや人付き合いの苦手さというビハインドを上回り、ボクを営業マンとして成功に導いた。20代で年収1,000万円は、世間一般では成功している部類だろう。
とはいえ、辛いものは辛い。ずっとやめたかったけど、ついに「辞める」と言えなかった。そうしたら、新規事業の「X部隊」に引っこ抜かれた。
そこで、新規事業の楽しさにのめり込み、ビジネス書で自主的に勉強するようになった。そうしたら運命が転がり込むように機会に巡り合った。
そして、ついに自分にしかできない大きな仕事をした。上から落とされた仕事でもなく、上司が持ってきた仕事でもなく、紛れもなく自分で作り上げた仕事を。
これがあらまし。
もし母が寿退社していたら、もしリーマンショックが1年遅かったら、厳しくも愛のある上司やお客さんに出会っていなかったら、もしあのとき営業をギブアップしていたら、今のボクはいない。
偶然にも点と点がつながって、類稀なる「黄金の経験」をすることになった。そして、新しい「生き様」を見つけた。
こういう発信をしてるから、ボクを「ビジネスが好きな人」と思っている人もいるかもしれないね。間違ってはいない。ビジネスは好きだよ。でも、厳密には違う。
ボクが本当に好きなのは、「自分の信念を具現化して、誰かを幸せにする活動」なんだ。
- 具体的な商品で、直接的に幸せにする場合は、「ビジネス」と呼ばれる。
- 絵や詩で間接的に伝える場合は、「アート」と呼ばれる。
- 信仰によって幸せにする場合は、「宗教」と呼ばれる。
ボクにとっては、ビジネスもアートも宗教も、表現の仕方が違うだけで根っこは同じ。自分の信念を、哲学を、正義を、他人に届けて、心の底から「ありがとう!」と言ってもらう。この創造的な活動が、どれだけ人の心を豊かにするか。
実際に事業を企画してわかったことだけど、規模の大きさはあまり頓着しない性分らしい。お金を儲けたいということでもない。家族を養う収入は欲しいけど、それ以上に欲しいとは思わない。
とにかく、自分の信じたものを具現化して、目の前の1人でも幸せにできることの素晴らしさを、尊さを、もっとみんなに知ってほしいと思った。
その技法は、あまり体系化されていない。いや、あるにはあるんだけど、多くの人は、あまり意味のないことだと思って素通りしている。けど、ボクはベンチャー立ち上げを通して、身をもって体験した。
「生き様を具現化する技術」
これこそが、ボクが本当に伝えたいこと。解き明かしたいこと。体系的に言語化するのは、ボクの義務であり使命だと思っている。
本当は「お金を稼ぐ方法」とかどうでもいい。ボクが目指しているのは、「棺桶に入る瞬間の自己採点を100に近づける方法」であって、そのためには生活費くらいは稼がなきゃいけないから、多少ビジネス色が出ているだけ。
これが、今のボクの「生き様」だ。これが、いま羅針盤の針が指し示している方角。
さて、ここでもう一度聞こう。
「あなたの生き様は何だ?」
文字通り、「生きてきた様」だから、答えはあなたの過去にある。
- あなたが大事にしてきたことは何だろう?
- あなたの原点は何だろう?
- あなたという人間を物語るエピソードは何だろう?
- あなたが記憶喪失になったとして、何を辿れば自分を思い出せるだろう?
じっくり考えてみてほしい。
その先に、あなたの生き様が投影された、あなたにしかできない作品がある。そして、その作品に感動するお客さんは必ずいる。すごく多くはないけど、絶対にいる。
こんな長ったらしい文章をここまで読んだあなたなら、きっと大丈夫。あなたらしい、ユニークで心躍るブランドは作れる。決してカンタンとは言わないけど、絶対に作れるよ。
長い自分語りでゴメンね。でも、ボクにしか伝えられない話かもしれないので、どうしても文章で残しておきたかった。
参考になれば嬉しいな!
もし何か感じ取ってもらえたら、こっそり感想もらえるとさらに嬉しい!
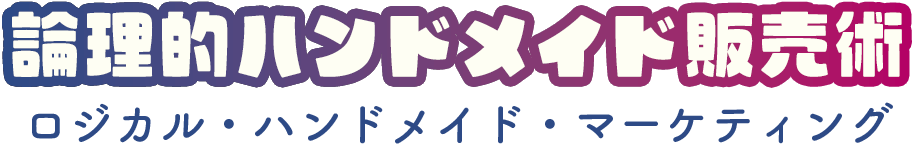
なおさんの物語を聞かせていただいてありがとうございました。凄い世界線で戦われてきたなおさん。そんな方から勉強できて、とても嬉しいです。
こちらのサイトに出会ってから半年が経ちました。それまで、メルカリでハンドメイド商品を販売していました、中途半端に。なおさんの文章を読みあさり、Creemaとminne、インスタを始めました。
今も迷った時は、こちらに立ち戻り、自分の頬を叩き気合を入れます。
今私がしている販売の仕方を客観的に見ても、なおさんから学んだことを素直に実践していて、可愛いなぁとさえ思います。でも売れません。まだまだ足りないことや出来ていないことがたくさんあるのだと思います。
久しぶりにこちらを覗いたら、新着記事があって嬉しかったです!今回の記事を読んで、これからもなおさんから学びたいと思いました。
私の生き様は「私が感じた感動を形に表現すること」。私はクリエイターです。こうやって生きることが何よりの喜びです。
長い昔話を読んでくださって、ありがとうございました!
なるほど、そうでしたか。「リエフォさんの感じた感動」とは何でしょうね。とても気になります。
リエフォさんが感じた感動は、当たり前ですが、ご自身の五感で感じ取った感動ですね。その感動をお客さんに伝えるためには、やはりお客さんの五感に訴える必要がでしょう。
リエフォさんがかつて感じた感動を色鮮やかに伝えるには、どんな作品を作り、どんな言葉を紡げばよいか?それを考え抜いて、アウトプットするのがクリエーターですね。
応援&期待しています!