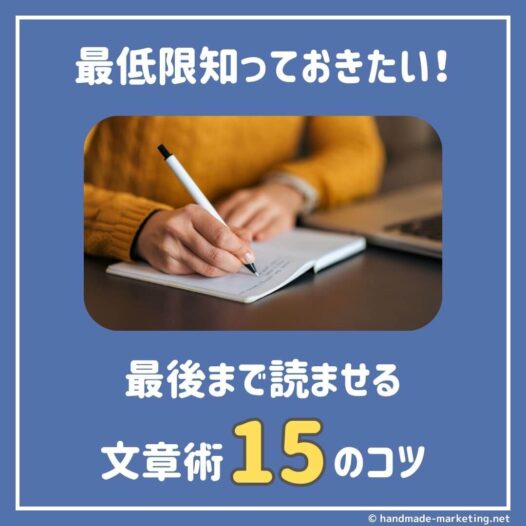
究極的には、文章の目的は最後まで読んでもらうこと。ある一文は、次の一文を読んでもらうために存在します。
「もういいや」と閉じられてしまったら、そこでゲームオーバーなんですね。
「ワタシはそんな上手な文章は書けない!」と思いましたか?
そうそう。モノづくりは得意なんだけど、文章となるとねぇ…
実は、ビジネスで美しい文章を書ける必要はありません。むしろオシャレな表現や、レトリックな言い回しなどは、かえって文章を読みづらくさせます。
最後まで読んでもらうためには、
- 読み手を惹き込む構成
- 読み手に負担をかけない文章
の2つを意識する必要があります。
前者の「読み手を惹き込む構成」は、シーンによって書き方が変わります。小説、モノを売るセールスレター、ブログ記事では、書き方が異なってくるでしょう。
ハンドメイド作家が学ぶべきはセールスレター
これはまた別の機会に解説するね
この記事で取り上げるのは、後者の「読み手に負担をかけない文章」。学術書や新聞は、スイスイ読み進められないですよね。これは読み手に負担を強いているからです。
言い換えれば、「読んでる途中で考えさせない文章」ですね。スラスラとつっかえることなく、最後まで読み切れる文章です。
読み手に負担をかけない文章の書き方は、基本的にどのシーンでも共通。
- SNS
- プロフィール文
- 作品紹介文
- ブログ
- イベントのPOP
- 動画の台本
で使いまわせます。ハンドメイド作家じゃなくても通用します。
実は、「読み手に負担をかけない、スッと頭に入ってくる文章」を書くのに、才能もセンスも必要ありません。ただいくつかのルールを守って書くだけ。
この記事では、ハンドメイド作家が「ここまでは知っておきたい文章術のコツ」を厳選しました。ボク自身がいつも意識しているテクニックでもあります。
ボクも文章で飯を食っている人間の端くれ。すでに、あなたが一生で書くであろう文字数の何倍も書いています。信用してもらって大丈夫です。
この記事の通りに実践すれば、読み手はストレスなく最後まで読んでくれますよ!
一度身につけば、一生使える!
ぜひマスターしておこう!
語り口調で書く
ハンドメイド作家が文章を書くシーンなら、「語り口調」で文章を書きましょう。
つまり、口に出しても違和感ない文章ということですね。
語り口調じゃない文章と比べるとピンと来きます。次の文章を読んでみてください。
❌【語り口調じゃない】
わたしは刺繍作家だ。デフォルメしたかわいい動物をモチーフとし、作品を制作している。犬と猫は特に得意だ。わんちゃん、猫ちゃん好きのお客さんには、満足いただけるだろう。
⭕️【語り口調】
わたしは刺繍作家です。デフォルメしたかわいい動物をモチーフに、作品を制作しています。犬と猫は特に得意!わんちゃん、猫ちゃん好きのお客さんには、ご満足いただけると思います♪
語り口調ではない新聞や活字っぽい文章は、頭にスッと入ってきづらいんですね。間違いではありませんが、ハンドメイド作家が文章を書くどのシーンにも向きません。
これはまぁそうだよね
YouTubeで一人語するイメージで書くといいかも!
基本的には、「です・ます調」になると思います。不特定多数のお客さんに声をかけるとき、いきなりタメ口は聞かないでしょう?
SNSならタメ口キャラもアリだと思いますが、プロフィールや作品紹介でタメ口は馴れ馴れしすぎます。
ただ、かしこまる必要はありません。バリバリに敬語を効かせる必要もありません。イメージとしては、「友達の友達」に話しかけるくらいの感覚がオススメです。
漢字を開く
「漢字を開く」という表現は、聞いたことない人が多いかもしれませんね。
「漢字を開く」とは、「ひらがな」で書いても違和感がない漢字は、「ひらがな」で書くということです。
- 何故→なぜ
- 貰う→もらう
- させて頂く→させていただく
- 〇〇という事→〇〇ということ
- 無い→ない
- した時→したとき
- 物→もの
- 所→ところ
といった具合です。
なぜそうするか?
フルで漢字にしてしまうと、文章が「黒っぽく」なって難解な印象を与えてしまうからです。昔の新聞記事や辞書は、黒っぽくて「ウッ」と感じますね。
なお、ひらがなとカタカナだけで「白っぽい」文章も、抑揚がなく読みにくいです。カタカナ用語が連発すると、白っぽくなりやすい傾向があります。
ただ普通に日本語を書いて、白っぽくなるケースはほとんどない
意識するのは、漢字を開いて黒っぽさを薄めること!
同じ文末は連続2回まで
同じ文末の表現が3回続くと、文章のリズムが悪くなります。音読するとわかりますが、幼稚な印象を受けるでしょう。
何も考えないと、
- です。
- ます。
ばかりになってしまいます。どっちも「す。」で終わるので、どうしてもリズムが悪い。
実際に見比べてみてください。
❌【同じ文末が続く】
イラストレーターのマナミです。「極彩色でサイバーな未来」がテーマです。SF好きな人にオススメです。
⭕️【文末にバリエーションがある】
イラストレーターのマナミです。「極彩色でサイバーな未来」がテーマ。SF好きな人にオススメです。
こちらは「体言止め」でリズムを変えています。
要するに、「文末のバリエーションを複数持っておきましょう」ということですね。
- でした。/ しました。(過去形にする)
- でしょう。(未来形or推定にする)
- ですね。/ ますね。(「ね」をつける)
- ですよね。/ ますよね。(「よね」をつける)
- ではないでしょうか?(疑問形にする)
- 体言止め(名詞や代名詞で終える)
- 用言止め(動詞や形容詞で終える)
などを織り交ぜて、リズムを作りましょう!
ひとつ注意点。「体言止め」は連発すると読み手に負担をかけるので、使うならピンポイントで!
読点(、)で区切る
読点(、)で文章を区切らないと、すっごく読みづらいです。これに関しては、国語の授業でも習いましたね。
しかし大人になって忘れてしまったのか、読点を打たずにダラダラ文章をつなげて書く人が一定数います。
❌【読点なし】
京都産の最高級のシルクで編み上げた振袖は艶やかな風合いと滑らかな着心地が魅力です。
⭕️【読点あり】
京都産の最高級のシルクで編み上げた振袖は、艶やかな風合いと、滑らかな着心地が魅力です。
書いている本人は問題ないかもしれないけど、読まされる方は苦痛でしかない
声に出して、あるいは心の中で音読してみて、自然と息継ぎする場所には読点を置いてください。
また、文章が短くても、同じ助詞が連続する場合は読点を打ちましょう。打たないと、文章が幼稚な印象になってしまいます。
- お昼に犬に餌をやった
- お昼に、犬に餌をやった
またまた、係り受けを明らかにするためにも、読点を使います。
- かわいい子犬とキリン
- かわいい子犬と、キリン
前者の文章だと、「子犬とキリンの両方がかわいい」ことになります。後者の場合は、「子犬だけがかわいい」ことになります。
長い文章は分割する
読点(、)を置いたところで、長い文章をダラダラ続けるのもやっぱりNGです。
新聞や書籍でも普通にあるのですが、読み手には優しくないですよね。
❌【分割しない】
京都産の最高級のシルクを、熟練の職人が編み上げた振袖は、艶やかな風合いと、滑らかな着心地が魅力です。
⭕️【分割する】
京都産の最高級のシルクを、熟練の職人が編み上げた振袖です。
艶やかな風合いと、滑らかな着心地が魅力です。
うえー、読みづらーい
「一文の読点(、)は2回まで」を目安にしましょう。
センテンスが長くなってしまう1つの理由は、1つのセンテンスの中に、2つ以上のメッセージが入ってしまっているから。原則は、「1センテンス=1メッセージ」です。
例えば、センテンスは短いですが「花子さんは、テニスが得意で、食べ歩きが趣味です」は、2つのメッセージが入ってしまっています。
「花子さんは、テニスが得意です。趣味は食べ歩きです」と分割すれば、それぞれのセンテンスにメッセージは1つになりますね。
とは言え、どうしても読点を3,4回使ってしまうシーンもあるにはあります。そうであっても、悪い文章を書いていると自覚しながら使うべきでしょう。
見出しをつける
お客さんは、初見では文章をざっと流し読みします。なんとなく眺めて、読む価値ありそうと判断したら、改めて冒頭に戻って読み始めます。
そのとき、何を拾い読みしていくかと言えば、「見出し」です。見出しを見て、文章がどんなトピックを含んでいるかを掴んだ上で、熟読するか否かの判断をするわけです。
「見出しのない新聞」を想像してみてください。
小さな文字が延々と連なっている。頭がクラクラしそうですね。よーく眺めないと、どこに何が書いてあるのか掴めません。
あまりに負担が大きいので、「読まない」という選択をするでしょう。
「何を当たり前の話をしているのか」と思われたかもしれませんね。
いやいや。ハンドメイド作家さんの書いた商品ページやブログを見ると、見出しがない文章がホントに多いんですよ。どこでトピックが切れているかが分からない文章が。
細かく改行してるかは関係ありません。ダラダラ文章がつながっていれば、改行していようがいなかろうが同じこと。改行を2回入れてスペースを空けてるから、なんて言い訳もなしですよ。
なお、マークアップ(WEBページ上の装飾)ができないケースが多いのは理解しています。その場合は、「記号」を使うと良いでしょう。
- 【見出し】
- ◉見出し
- 〜見出し〜
のような感じですね。「どこに、どんなトピックが書かれているか?」のヒントとして、見出しをつけてください。
さもなくば、せっかくお客さんを惹きつける文章を書いても、お客さんに素通りされちゃいますよ!
並列する内容は箇条書き
並列する内容が「2つ以上」続く場合は、箇条書きにすると読みやすくなります。
ぜひ比較してみてください。
❌【箇条書きなし】
当店のこだわりは、高品質な素材、無駄のない機能美、色彩の鮮やかさの3点です。
⭕️【箇条書きあり】
当店のこだわりは、次の3点です。
- 高品質な素材
- 無駄のない機能美
- 色彩の鮮やかさ
文章がツラツラ続くと、視覚的に「ウッ」と来るんですよね。新聞や書籍を読んでいると、途中で疲れてきませんか?
箇条書きには、イラストや図解と同じような効果があります。文章の中に、ちょっとしたオアシスが生まれるんです。
目に優しい箸休め!
ちなみに、箇条書きにも「見出し」と似た効果があります。
箇条書きの箇所は、流し読みをしていても、自然と目に止まりやすい。そのため、大切なこと(作品のセールスポイントなど)は、箇条書きにすると良いでしょう。
少々突っ込んだ話をすると、人間が同時に覚えておける情報の数は、「4±1」と言われています。それ以前は、「7±2」と言われていましたが。
そのため、箇条書きの数は、下限の「3個」がオススメ。これより増やすと、スッと頭に入らない人が出てくるので。
逆に、盛りだくさん感を伝えたければ、上限の「9」を超えて、「10個」にしても良いね
「豪華10大付録」みたいな感じ。なんか凄そうでしょ?
改行は長すぎず短すぎず
改行はバランス良く。長すぎても、短すぎてもいけません。
新聞は、改行なしで文章が続きます。画面びっしり文字が詰まっている映像は、「ウッ」と来てしまいますね。
その反動か、一文ごとに改行する人も出てきました。「スマホは一列に表示される文字が少ないので、全部改行せよ!」と教えている人もいるみたいです。
X(旧Twitter)みたいに短い文章ならそれでもいいでしょう。
しかし、一定量の文章で、句点(。)がつくたびに改行されると苦痛です。どの文章までが、同じグループなのかわかりづらいからです。
また改行すればするほど、文章が縦に伸びていきます。スクロール量が増えるのも、離脱の原因になってしまいますね。
- PCで2〜3行
- スマホで3〜4行
が、ちょうど良い改行の目安です。
原則は、文章の意味が分かれるところで改行しよう
その上で、ちょうど良い行数で改行できるのが理想!
論理を飛躍させない
文章の論理が飛躍すると、読み手の頭に「?」が浮かびます。スイスイ読み進めていても、そこで流れが止まってしまいます。
文章の論理とはつまり、文章の意味が、「A→B→C」とつながっているところを、「A→C」に一足飛びにつなげないということです。
❌【論理の飛躍あり】
世に出回っている梅干しは、偽物がほとんどです。そんな中、当店の梅干しは本物です。
⭕️【論理の飛躍なし】
世に出回っている梅干しは、偽物がほとんどです。干さずに、調味液につけているだけ。梅干し本来の旨みと栄養素は失われています。当店の梅干しは、昔ながらの製法で作られた本物です。
何が偽物で、どうなると本物なのかがわからないね
「接続詞を省いても伝わるか?」を確認すると良いでしょう。
- しかし
- そのため
- なぜなら
- そして
- これにより
- そんな中
などの接続詞がないと文章の意味が通らないなら、強引に文章をつなげている可能性があります。論理が飛躍してしまってるかもしれません。
もちろん同じ日本語ネイティブ同士なら、言わんとしていることは理解できる
でもそれに甘えて、文章を雑につなげてはいけないよ
逆説の接続詞を連発しすぎない
逆説の接続詞とは、「しかし」「でも」「だが」「ですが」「ただ」などです。前の文章で書いた内容を、後ろの文章で覆すときに使います。
丁寧に説明しようとしたり、論理的に説明しようとすると、逆説でつなげるシーンが出てきます。ボクもよく使います。
例えばこんな感じですね。
❌【逆説文が3回連続する】
1層のみのコーティングで済ませる作品が一般的ですが、当作品はよりツヤを出すために、3層のコーティングを施しています。
手間はかかりますが、身につけたときに、より一層華やかに映ります。
その分少々お高めにはなりますが、ご満足いただけると思います。
⭕️【逆説文が連続しない】
1層のみのコーティングで済ませる作品が一般的ですが、当作品はよりツヤを出すために、3層のコーティングを施しています。
身につけたときには、より一層華やかに映ります。
お手間の分少々お高めにはなりますが、ご満足いただけると思います。
ただ、この逆説が連発すると、文章が偏屈になってしまい、あまり性格の良くない人が書いたような印象を与えてしまいます。読んでいて、あまり気持ちの良い文章にならないんですね。
逆説を使うことは、全くもって悪ではありません。しかし、連発は避けた方が、印象は良くなります。
理屈こね太郎のボクもやりがちなので、注意しなきゃ(汗)
係り受けの距離を縮める
文章の中には、「係る言葉」と「受ける言葉」があります。
両者の距離が離れてしまうと、文章がスッと入ってこなくなります。
説明ではわかりづらいので、例を見てみてください。
❌【係り受けの距離が長い】
なぜ、純白に輝く天然パールは、いつの時代も世の女性を魅了してきたのか。
⭕️【係り受けの距離が短い】
純白に輝く天然パールは、なぜ、いつの時代も世の女性を魅了してきたのか。
ボクはかれこれ何年も文章を書いていますが、何も考えずに書いていると、この係り受けのルールを忘れてしまうことがあります。
文章を見直したときに、「あ、係り受け離れてんな」と気づくことが結構あります。
慣れてる人間でもこれなので、特に注意が必要かと!
専門用語は的を絞って使う
絶対に守ってほしい約束が、「読み手が知らない専門用語を、説明なしに使ってはいけない」です。
カタカナ用語のオンパレードの文章は、最悪の文章の1つでしょう。基本的には、小学生でも知っている単語だけで文章を構成すべきです。
あえて難しい単語とか古風な言い回しを多用する人いるよね
自分に酔ったエゴイストが書く最悪の文章だよね
ただし、専門用語を使うなと言っているわけではありません。むしろ、大事なポイントで使う専門用語は、あなたの武器になります。
例えば、次の文章を読んでみてください。
当店の醤油ラーメンのスープには、フランス料理の「ブイヨン・ド・レギューム」の技法が用いられています。
「ブイヨン」は出汁、「レギューム」は野菜を意味しています。つまり野菜でとった出汁のこと。コンソメスープの元にもなります。
他店では決して味わえない、優しいけどパンチがあるコク深いスープをお楽しみください。
「ブイヨン・ド・レギューム」は、99%の日本人が知らない専門用語です。
もちろん説明なしに使うのは御法度ですが、きちんと説明を添えれば、ものすごく説得力が増す気がしませんか?
本当に問題になるのは、「専門用語を使うこと」ではなく、「専門用語の説明に専門用語を使うこと」なんですね。
大事なポイント使う専門用語は、読み手に新しい世界への扉を開かせます。そして、そんな未知の世界の存在を教えてくれたあなたに、特別な信頼を寄せるでしょう。
素材だったり、技法だったり。その道の人しか知らない専門用語ってあるよね
ライバルと差別化するポイントでは、専門用語で違いを見せつけたいね
指示語(あれ/これ/それ)は少なめに
「あれ」「これ」「それ」などの指示語は、読み手に「えっと、どれのことだっけ?」と一瞬考えさせてしまいます。
文章をスイスイ読み進めているときに、目の前に急に大きな岩が登場する感じ。そこで流れが止まってしまうんですね。
指示語が指している対象が、文章の随分前に登場していると、巻き戻って確認しなければならないこともあります。
ただし、指示語を「0」にするのは難しいでしょう。まずは、なるべく使わないように意識するところから始めてください。
話し言葉だと、ついつい使っちゃいがち!気をつけよう!
あいまいな言葉は少なめに
様々な意味に受け取れる「あいまいな言葉」は少なめにして、なるべく「具体的な言葉」を使いましょう。
なるべく避けたいあいまい言葉
- あいまいな名詞
「こと」「もの」「人」「場所」 - あいまいな動詞
「する」「やる」 - あいまいな形容詞
「すごい」「美しい」「きれい」「やばい」 - あいまいな助詞
「とても」「非常に」「圧倒的に」
「あいまい」ということは、その言葉が広く色んなものに当てはまるということ。そうではなく、ピンポイントに、そのものだけを指す言葉に変換しようということです。
ハンドメイドの現場では、次のように変換ができます。
- 作品→スマホケース
- 当ブランド/当店→ルイヴィトン(実際はあなたのブランド名)
- 素材→花材/木材/生地
漠然とした形容詞も、雰囲気を伝えづらいので避けるべきです。
- かわいい→ポップな
- かわいい→ゴシックな
- かわいい→デフォルメされた
- 美しい→色鮮やかな
- 美しい→黄金比に沿った
- 美しい→艶々と光り輝く
程度を示す表現も、なるべく具体的な数字を使う方が良いです。
- 約半数の→53%の
- ほとんどのお客様が→10人のうち9人のお客様が
- 100個近くの→98個の
- 軽い→1グラム(1年玉1枚分!)
意識したら、いかにあいまいな言葉に頼って生きているかがわかりそう…
ま、ボクも人のこと言えないくらい使ってるんだけどね
なお、ここで出した「あいまい言葉」はあくまで一例です。
例えば、何気なく使う「おいしい」も、あいまいな言葉ですね。
あなたが普段の食事で、「おいしい!」「うまい!」と言うのは、何の問題ありません。しかし、これがグルメリポーターのコメントなら失格です。
- 「外はカリッと、中はフワッと」とか
- 「爽やかな柚子の香りが鼻を抜ける」とか
- 「ムチッとした食感と共に、小麦の風味が押し寄せてくる」とか
もっと具体的な言い様は、いくらでもあるわけです。
にもかかわらず、十把一絡げに「おいしい!」で終わらせるのはいかがなものでしょう?小学生でも務まりそうですね。
仕事で書く文章なら、もっと具体的な表現に変換できないか、言い換えると、「もっと解釈の範囲が狭い単語に置き換えられないか」を常に模索しましょう。
あるいは、「この単語をもっと細かく分解できないか」と考えても良いですね。「子供」という単語を「息子や娘」と分解するだけでも、読み手はよりイメージしやすくなるのです。
計算させない
数字を扱う場合は、読み手に計算させてはいけません。
❌【計算させる】
- 定価9,800円が30%OFFに!
- 1箱12粒入りが計4箱
⭕️【計算させない】
- 定価9,800円が6,860円に!→30%OFF(2,940円引き)
- 1箱12粒入りが計4箱(48粒)
読み手の負担になり、そこで止まってしまうからです。読み手に脳みそを使わせる文章を書くべきではありません。
上記は値引きの例を出しているけど、ハンドメイド作家は値引きはしない方が良いよ!
あくまで例として受け取ってね!
また耳寄りな情報として、人間は「%」の表記を理解するのが得意ではありません。割合を示す単位なので、必ず計算することになりますから。
なので、「満足度97%!」と書くよりも、「100人中97人が満足しました!」と書く方が、読む人にはスッと伝わるのです。
半角or全角のルールを揃える
数字やアルファベットの全角or半角は、統一しましょう。
- あるところで「11色」
- 別の箇所では「3日以内」
と表記するのはNGです。
半角と全角のルールが統一されていないと、「この人は、細かいところに気を配れない人だ」という印象を与えます。
ハンドメイド作家なら尚更。美意識のない作家だと思われてしまうでしょう。あなたのブランドを傷つける結果になります。
数字とアルファベットは、本来半角文化の文字。半角に統一するのが自然です。ただルールを守っているなら、全角で表記してもOKです。
表記揺れをなくす
同じ意味を持つ複数の単語が混在している状態を、「表記揺れ」と呼びます。
- 結婚式
- 挙式
- ウェディング
- (単に)式
は、いずれも同じ意味で使われますね。
また読み方は同じだけど、文字にしたときの表記揺れもあります。
- 受付 / 受け付け
- バラ / ばら / 薔薇
- 寿司 / 鮨 / すし
先に紹介した、全角or半角が統一されていないのも、表記揺れの一種。
表記揺れは、読み手に負担をかけます。避けましょう。
主語=自分の文章を減らす
お客さん向けの文章では、一人称をなるべく使わないことです。
つまり、「私」や「当店」は、なるべく使わないということですね。
では誰が主語になるかと言えば、もちろんお客さん。
日本語の特徴として、主語はしばしば省略されます。省略していたとしても、主語がお客さんになる文章を書きましょう。
| 「主語=自分」から | 「主語=お客さん」へ |
|---|---|
| わたしが考え抜いた | お客様のために考え抜かれた |
| 3色を取り揃えています | 3色からお選びいただけます |
| 〜をご提供します | 〜が手に入ります |
| 〜の指定は承っておりません | 〜は指定いただけません。予めご了承くださいませ |
| 〜を施して、耐久性を向上させました | 〜による高い耐久性により、少々雑に扱ってもへっちゃらです |
なぜか?
お客さんは、売り手であるあなたに関心があるのではなく、自分自身の人生や生活に、どう役立つかに関心があるからです。当たり前ですよね?
読み手とは、どこまでも自己中心的なのです。
と言っても、主語=自分が「0」にはならない。なるべく使わないって意識でOKよ
「あなた」を使う
ライティングの世界では、「みんな」や「お客様」という呼びかけはあまりしません。
代わりに「あなた」を使います。つまり、「二人称複数形」ではなく、「二人称単数形」を使うわけですね。
どんな文章も、「売り手」から「そう、今この文章を読んでいるそこのあなた!」に向けて書いている。1対1のお手紙なので、不特定多数に向けた呼びかけはしないのです。
例えば、学校の先生から、「整列が遅れたのは、みんなのせいだぞ!」と言われたら、「ふーん。とりあえず神妙な顔しとくか」くらいにしか思わないですね。
これが、「整列が遅れたのは、お前のせいだぞ!」と指さされたら、「うお!マジかよ」と、思わず背筋を正してしまいます。
この単純な例だけでも、対象が1人に絞られている方が、読み手を文章に集中させる効果があるとわかりますね。
英語だと「You」だけでわかりやすいですが、日本語だと「君」「貴殿」「貴様」「そなた」「お前」などなどあります。が、まぁ使えるのは「あなた」くらいでしょう。
趣旨は、読み手に「これ、自分1人に向けて書いてくれてるな」と思わせること。なので、名前がわかっているなら、「〇〇さん」と呼んであげる方が良いですね。
ただ、なかなかそうはならないので、「あなた」を使うのがベターよ
まとめ
最後まで読んでもらうための文章術でした!
1つ1つはそんなに難しくなさそう!
量は結構あるけどw
これでも厳選したんだけどね
いきなり全部は難しいから、1つ1つマスターしていこう!
この記事をまとめます。
最後まで読ませるための文章のコツ
- 語り口調で書く
- 漢字は開く
- 同じ文末は連続2回まで
- 読点(、)で区切る
- 長い文章は分割する
- 見出しをつける
- 並列する内容は箇条書き
- 改行は長すぎず短すぎず
- 論理を飛躍させない
- 逆説の接続詞を連発しすぎない
- 係り受けの距離を縮める
- 専門用語は的を絞って使う
- 指示語(あれ/これ/それ)は少なめに
- 抽象的なふんわり表現を避ける
- 計算させない
- 半角or全角のルールを揃える
- 表記揺れをなくす
- 主語=自分の文章を減らす
- 「あなた」を使う
まずはこれらのルールを知っておくことが大切です。
実際に文章を書いていくと、ルール通りに書けないシーンも出てきます。
- どうしても、「です。」の文末が3回続いてしまう
- どうしても、読点(、)が3回以上の長い文章ができてしまう
- 文字数上限が厳しく、漢字を開く余裕すらない
などなど。ボクもよくあります。
しかし無意識にルールを破って書くのと、「あぁ、ルール破っちゃうけど、ここはしょうがない」と理解した上で書くのでは、天と地ほどの差があります。
このちょっとした意識が、あなたの文章をどんどん洗練させていくのです。
この記事で紹介した文章のコツは、基本的にどんなシーンでも有効です。
- SNS
- ブログ
- 取引先とのメール
- プレゼン資料
などなど。ぜひ今日から意識してみてください!
(おまけ)文章をセルフチェックする方法
最後に、「読みやすい文章が書けているか」をセルフチェックする方法も伝えておきましょう。
今回紹介したすべてのルールを拾えるわけではありませんが、やれば必ずと言って良いほど、文章を改善するヒントを得られます。
セルフチェックの方法
- 音読する
→文字だと違和感に気が付かない箇所も、声に出して読むと気づける - ドキュメントソフトにペーストする
→WordやGoogleドキュメントに文字を転記すると、文法誤りや誤字脱字の箇所を指摘してくれる - 英訳→再度邦訳する
→自動翻訳をすると、まわりくどい表現や曖昧な言葉遣いをした箇所が、意図しない意味で翻訳されることが多い
個人的にオススメなのが、「英訳→再度邦訳する」です。
まず、書いた文章を、ネット上の翻訳ツールで英訳します。英語をスラスラ読めない人はこのままじゃしんどいので、英訳した文章をそのまま再度日本語に訳します。
精度的には、DeepLやChatGPTの方が高いのですが、あえてぎこちないGoogle翻訳を使うのも手。粗探しをするには、粗く翻訳してくれた方が見つけやすかったりします。
なお、この方法は、わかりにくい日本語表現の箇所を見つけるためのワーク。最後に出力された日本語訳の文章を、そのまま使うわけではないですからね。
SNSのように、日々流れていく文章に関しては、ここまでしなくても良いかもしれません。少なくとも、ボクはSNSでこのセルフチェックはしません。
一方で、一度書けばしばらく使い続ける商品ページの文章などは、このセルフチェックを通す価値があるでしょう。
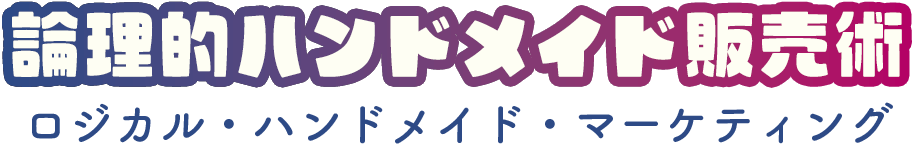
コメントを残す